アルパックニュースレター180号
地域から少子高齢化への対応を考える(その2)~出生率を高める女性就業率に影響を及ぼす3つの要因~
少子高齢化が地域の活力やインフラ管理等に及ぼす影響が大きいため、関西の市町村を対象に、まずは少子化緩和の観点から考察を進めることとし、前号(その1)では、女性就業率が高いと出生率も高くなる傾向があることを、様々なデータから確認し、出生率を高めるためには、「女性が就業しやすい環境を用意する」ことが重要だと述べました。
今号では前号に続いて、女性就業率に影響を及ぼす要因について、考えてみることにします。
保育サービスの効果と限界
女性の就業率を高めるためには、まず保育所を用意することが考えられますので、市町村別の0歳~6歳児数(国勢調査2010年)に対する認可保育所利用者数(厚生労働省保育課調べ2012年)の比率を「保育所利用率」とし、女性就業率との関係を下のグラフのように整理してみると、ある程度の相関が確認でき(相関係数R=0.40)、保育所サービスの充実が重要であることがわかります。
ただし、保育所利用率との相関が、それほど強いわけではありませんので、保育サービスだけが女性就業率に影響を及ぼす要因だとは考えられません。
そこで、保育所利用率との関係が弱そうな市町村を眺めると、産業が不振で働く場が少ないと考えられる市町村では女性就業率が低く、祖父母との同居あるいは近居が多く祖父母による子育てフォローがあると考えられる市町村では女性就業率が高いことから、「身近な就業の場」や「実家の子育てフォロー」について、分析を進めてみます。
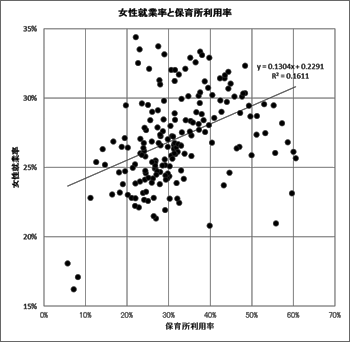
資料:就業率と0~6歳児数は国勢調査(2010年)
保育所利用者数は厚生労働省保育課調べ(2012年)
身近な就業の場の効果
身近に就業の場があることが女性就業率を高めると考え、女性が働く場が身近にあることを示す市町村別の指標として、女性人口(常住地ベース)に対する女性従業者数(従業地ベース)の比率を用いると、女性就業率との明らかな相関が下のグラフのように確認できます(相関係数R=0.62)。
ただし論理的には、この指標は市町村の規模にも影響され、さらに就業の場が自市町村内になくても、近隣市町村にあれば「身近な就業の場」となる可能性がありますので、この指標だけで身近な就業の場の重要性を述べるのは十分ではありません。
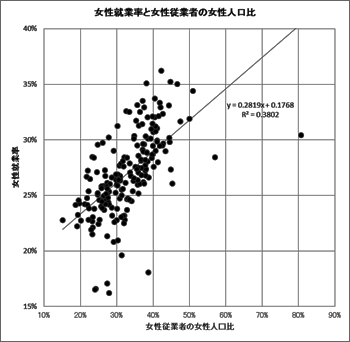
資料:国勢調査(2010年)
そこで、パーソントリップ調査(注)の市町村別平均通勤時間と女性就業率の相関を下のグラフのように整理すると、極めて明確な相関が確認でき(相関係数R=0.73)、平均通勤時間が少ない市町村ほど、女性の就業率が高くなっていることがわかります。
すなわち、女性の就業率を高めることに対して、長時間通勤を強いる住宅の郊外化が、障害になっていることが示されていると考えられます。
注:京阪神都市圏パーソントリップ調査は10年ごとに行われ、最新(2010年)の市町村別平均通勤時間(出勤の平均時間)は、まだ公開されていないため、構造的な変化は少ないと考えられる2000年データを用いています。なお、2000年調査は、関西の外縁部の市町村を対象範囲にしていませんが、関西の7割程度の市町村はカバーされています。また、女性だけの通勤時間が集計できれば、この相関係数はさらに高くなると思われます。
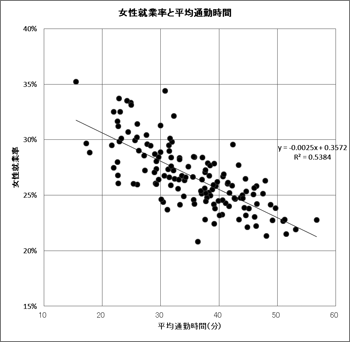
資料:就業率は国勢調査(2010年)
平均通勤時間はパーソントリップ調査(2000年)
実家のフォローの効果
実家と同居あるいは近居することによって、実家による子育てフォローを受けることが出来ると、女性が就業しやすくなると考えられます。しかし、「実家との同居や近居」を示す指標はありませんので、「3世代住宅が多い市町村は、実家と同居あるいは近居している子育世帯が多い市町村である」と仮定し、3世代世帯率(普通世帯に対する3世代世帯の比率)を代替指標とすれば、下のグラフにみるようにある程度の相関が確認でき(相関係数R=0.43)、実家による子育てフォローも女性就業率を高めている可能性があると思われます。
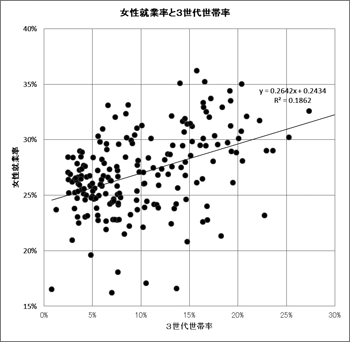
資料:国勢調査(2010年)
出生率低迷を考えるもう一つの切り口
前号(その1)と今号では、「女性の就業率」を切り口に、出生率を高めるには女性の就業率を高めることが有効であること、さらに女性の就業率が高い市町村は、保育サービスが用意され、身近に就業の場があり、実家の子育てフォローが比較的多いと思われることを示しました。
しかし、この出生率を巡っては、もう一つの切り口があります。それは「未婚化・晩婚化」で、「結婚しないので子どもが生まれていない」「晩婚のため、年齢的制約から子どもが生まれていない」などの指摘があります。次号では、この「未婚化・晩婚化」を切り口に、もう少し少子化の原因を考えてみます。
アルパックニュースレター180号・目次
寄稿
ひと・まち・地域
- 地域から少子高齢化への対応を考える(その2)~出生率を高める女性就業率に影響を及ぼす3つの要因~/代表取締役社長 森脇宏
- 皇居ランの問題にまちづくりのアプローチで取り組む/都市・地域プランニンググループ 坂井信行
きんきょう
- 景観を通じたにぎわいづくり社会実験を行いました/公共マネジメントグループ 橋本晋輔
- 旧水井家住宅を活用してお茶会を開催しました/地域再生デザイングループ 岡崎まり
- 地域の魅力を巡る、まち歩きコースをつくってまちの皆に紹介しよう~ワガヤネヤガワ大学「まち案内人講座」~/地域再生デザイングループ 羽田拓也







