アルパックニュースレター180号
『まち再生の術語集』
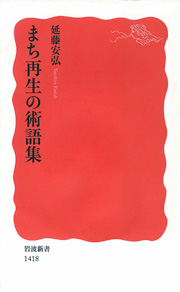
『まち再生の術語集』
幻燈会の雰囲気を疑似体感
筆者の延藤先生と言えば、あの魅力的で刺激的、そして楽しさあふれる幻燈会です。幻燈会のあの雰囲気に身を投じた方も多いのではないかと思います。幻燈会体験者であれば、本書を読みだすとすぐに先生のあの名口調が頭の中に響きます。未体験者であっても幻燈会の雰囲気の一端を感じることができるのではないでしょうか。
まち再生の三大栄養素とコミュニティビタミン
さて、本書は、「楽しさと遊び」「つぶやきをかたちに」「知恵の育み合い」「トラブルをドラマに」の4つの章立てに分かれています。これは、先生が本書中で定義されている「まち再生の三大栄養素」の視点に基づき構成されているものです。
まち再生の三大栄養素とは、【楽しさや遊び、花・食・美などを通じた「喜び」】、【助け、助けられ、知恵を育み合う「共生」】、【トラブルをドラマに変える源泉となる「意志」】であります。そして、この三大栄養素の潤滑油として働く「コミュニティビタミン」が不可欠であるとも言われています。
例えば、三大栄養素の機能を刺激し促す役割を果たすコミュニティビタミンとして「絵本」「幻燈会」「笑い」「リスペクト」などが必要であり、また、「想像力」「聞く耳を持つ」「必死のパッチ」といった免疫力を高めるビタミンを摂取すれば、シンドイ状況を克服し、トラブルをエネルギーに変える効果を果たすということであります。
自在に往還できる「UICP」
本書には、住民参加における意識発展のキーワードとして「UICP」というキーワードが盛り込まれています。
「UICP」とは・・最初は「無関心unwareness」から始まり、出来事的推移の中に受動的に「巻き込まれinvolvement」、多様な経験ののち対象への愛の自覚と「参加participation」に至り、トラブルをひきうけ乗り越えていく「責任ある参加commitment」に赴く、というプロセス。
広島の可部におけるローカル線再生の事例においては印象的なつぶやきが紹介されています「どんなに小さなことでも、動き出すとマサツがおこるものです。でも、私たちは一歩踏み込んで小さなことをやってみました。すると不思議なことに、誰かが走り出すと、明るく楽しく動き始める人が続きます。」
「無関心」から「巻き込まれ」、「能動的な参加」へと展開していくプロセスは、水の流れや渦、水玉の集まる様が想起されます。
UIPCの概念として共感を覚えるのは、個人の状況に応じて関わり方を自由に選択できる概念であるということ。「P(参加)」や「C(責任ある参加)」を強いられると長続きしない。時に応じて「無関心」から「責任ある参加」を自在に往還できるということが大切なのです。
まちの術語たちが未来に向かう道筋を照らす
本書の前書きには、「まち再生の術語集として、人々が物語を生きる「心の習慣」を養う「心に届く言葉」をさがしていきたい」と記されています。
まち再生の三大栄養素とコミュニティビタミンの例をはじめとして、本書にはまちづくり・まち育てに取り組む上で参考にすべきたくさんの「術語」が星座のように散りばめられています。私たちが、まちづくりやまち育ての場面に関わるときに、「最初の一歩をどう踏み出すか」「仲間をどのように広げていくか」「活動を継続していくにはどうするか」「異なる意見の対立をどのように乗り越えていくのか」など、様々な壁にぶつかりますが、本書にちりばめられているきらきらと輝く「術語」たちが、夢のある未来に向かう道筋を照らしてくれていると思います。
アルパックニュースレター180号・目次
寄稿
ひと・まち・地域
- 地域から少子高齢化への対応を考える(その2)~出生率を高める女性就業率に影響を及ぼす3つの要因~/代表取締役社長 森脇宏
- 皇居ランの問題にまちづくりのアプローチで取り組む/都市・地域プランニンググループ 坂井信行
きんきょう
- 景観を通じたにぎわいづくり社会実験を行いました/公共マネジメントグループ 橋本晋輔
- 旧水井家住宅を活用してお茶会を開催しました/地域再生デザイングループ 岡崎まり
- 地域の魅力を巡る、まち歩きコースをつくってまちの皆に紹介しよう~ワガヤネヤガワ大学「まち案内人講座」~/地域再生デザイングループ 羽田拓也







