アルパックニュースレター181号
『デモクラシーを〈まちづくり〉から始めよう』
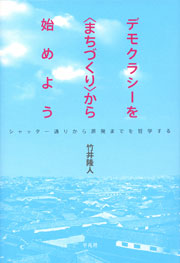
『デモクラシーを〈まちづくり〉から始めよう』
幻コミュニティ=仲良し
私たちは日頃、各地のまちづくりに関わらせていただいていますが、現場でよく使うフレーズに次のようなものがあります。
「まずはコミュニケーションを深めてコミュニティを意識しましょう」
この背景には、コミュニケーションの希薄化が自分の住むまちへの関心をも低下させ、コミュニティの崩壊(とまではいかないにしても少なくとも弱体化)を招いたという前提があります。そしてそれは、まちづくりにおいてコミュニティ
を重視する価値観へとつながっています。
こうした価値観に対して、本書では「コミュニティ=仲良し」に過ぎず、社会(ここではまちづくりの主体となる共同体)の組成原理としては不十分、かえって害悪をもたらす可能性すらある、という刺激的な主張が展開されています。
コミュニティは排他的
著者の主張はこうです。まちづくりは「コミュニティ=仲良し」をベースとする共同体が担っていくべきであるという考え方には疑問がある、なぜなら、仲良しというのは本来排他的なものであり、また全ての人と分け隔てなく仲良しになることは不可能だから。
つまりこういうことです。「成熟社会のまちづくりは多様な主体が協働で取り組んでいくことが大切」という考え方は社会の共通認識となっています。まちづくりの取り組みでは、外部にもネットワークを広げていこうとするオープンな姿勢が必要です。
しかし、まちづくりの主体となる共同体の構成をコミュニティにおき、かつ「コミュニティ=仲良し」だとすれば、コミュニティづくりを進めれば進めるほど、つまり仲良しの度合いを深めれば深めるほど、コミュニティの外の人を排除する方向へと向かい、まちづくりにおけるオープンなスタンスが損なわれるという矛盾にぶつかってしまうのです。
まちづくりに必要なデモクラシー
こうしたこともあって、まちづくりの主体となるべきは民主的な政治を担う共同体、つまり私的政府であるべきだ、というのが著者の主張です。まちづくりはデモクラシーだと。まちづくりの主体となる共同体の組成原理は、あくまでも共通の価値や目標であるべきだということです。
典型例はゲーテッドコミュニティやオートロックのあるマンションです。これらは住民の生命と財産を守るという共通の目的のため、合意に基づき管理が行われています。全ての地区は、ゲーテッドコミュニティ(ゲートそのものをつけるという意味ではなく)を目指すべきだとも。
ほどほどの仲良しはどうでしょう
マッキーヴァーによる伝統的な定義では、コミュニティは統合的で、特定の目的を持つアソシエーションとは違うということになっています。しかし、目的を持たないがために親睦団体に堕したのではないか、という著者の指摘にはうなずけます。コミュニティは、まちをよくするという「目的」を共有するべきです。私も常々アソシエーション的なコミュニティが必要だと考えています。
シャッター商店街の再生には商店側の努力と周辺住民がその店で購入することの約定が必要、マンション紛争は高さ規制をしておかなかった「不作為」 が問題、すべての問題を警察や行政など第三者に任せ切ってしまう社会制度が問題、といった著者の指摘は全面的に支持します。これらに共通して求められているのは、人ごとにしない姿勢や当事者意識です。では、当事者意識はいかに育まれるのか。ポイントは地域への愛着でしょう。そしてそれは人を排除しない寛容なコミュニティにおいて醸成されるはず、と考えるのはロマンチストに過ぎるでしょうか。
仲良し過ぎるのは弊害があるなら、ほどほどに仲良しのアソシエイティブ・コミュニティをめざしてみるのも良いかもしれませんね。
アルパックニュースレター181号・目次
ひと・まち・地域
- 地域から少子高齢化への対応を考える(その3)~出生率低下を推し進めている未婚化・晩婚化~/代表取締役社長 森脇宏
- 「隠れキリシタンの里 千提寺さと巡り」を開催しました/地域再生デザイングループ 岡崎まり・中塚一・嶋崎雅嘉
きんきょう
- 秋のバルフェス+あべのハルカスバルin阿倍野・天王寺の開催をお手伝いしています/地域再生デザイングループ 中塚一・西村創・羽田拓也
- 西京銭湯部隊沸いてるんジャー参上!!/地域再生デザイングループ 嶋崎雅嘉
- お盆/名誉会長 三輪泰司(NPO平安京・代表理事)







