アルパックニュースレター171号
人口減少時代における 土地開発公社のあり方を考える
土地開発公社をめぐる環境の変化
昭和30年代から40年代の高度経済成長期は、都市部の地価が急激に上昇していく中で、道路や公園などのまちづくりに係る公共事業用地の先行取得が必要とされました。昭和47年には、土地の先買い、土地開発公社の創設などを主な内容とする「公有地拡大の推進に関する法律」が制定され、これを契機に土地開発公社が全国各地で設立、最も多い時期には、1,500を超える市区町村の土地開発公社が設置されていました。
しかし、公社を取り巻く環境は著しく変化し、平成22年の三大都市圏における地価は、住宅地・商業地ともにピークであった平成3年に比べて大幅に下落。今後の人口減少社会においては、一部の地域を除いて土地の需要も減り、地価の上昇を見込むことは難しくなってきています。
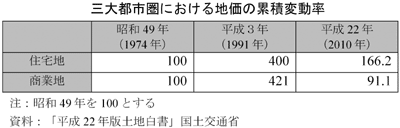
地価下落の中で不良資産化する「塩漬け土地」
また、景気の低迷等による自治体の財政悪化により、当初想定されていた事業が予定通り進まない事態も増えてきていることから、公社保有地の買い取りが遅れ、いわゆる「塩漬け土地」が増えて、平成21年度末の金額ベースで「5年以上保有額」は保有額の80%、「10年以上保有額」は同68%にまで上昇しています。
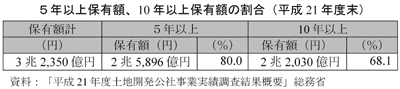
三セク債による公社解散の動き
地価上昇を前提に公共用地の先行取得を担ってきた土地開発公社の経営環境は、ますます厳しくなってきており、総務省では、近年、土地開発公社のあり方について、次のような働きかけを行ってきています。
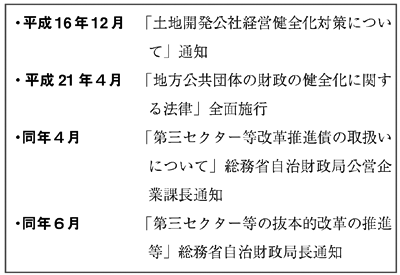
とりわけ、平成21年度から平成25年度までの時限措置として、「第三セクター等改革推進債(三セク債)」が創設されたことにより、土地開発公社に関しては、その解散または業務の一部廃止の場合に三セク債の発行を認められることになり、これを活用して、平成22年度から公社の解散等の動きが現れてきました。
「解散ありき」の議論ではなく、公社の現状と今後の役割を冷静に見直す
昨年、明石市土地開発公社(兵庫県明石市)において、公社のあり方検討に関するお手伝いの機会を得ました。その際、公社の解散・見直しに係る全国の様々な事例を見聞きする機会に恵まれました。
そこで明らかになったことは、公社の解散については、日々、金利負担が増えていく状況の中、「スピードある判断」が要求される一方で、公社の役割が既存の行政機構で代替可能なのか、保有地の処分についてどのように対応していくのか、行政本体の財政状況と一体的に改革できるのか、といった「内部調整」の重要性です。
まちづくり全体の中で公社保有地のあり方を考える
公社保有地の中には、事業計画が中止となって、使い道の無くなった土地が存在する場合があります。一般的には、売却することによって、少しでも債務返済や自治体の財政状況の「足し」にすることが考えられますが、簿価に対する実勢価額が大幅に下落した昨今では、多額の売却損を生み出してしまう場合が多いのが現状です。
そこで、もう一度、これからの地域の視点や参加による新しいまちづくりの中から、そのまちの振興全体を眺めてみたときに、公社保有地が「市民の豊かな暮らしに結びつく土地として活用ができないか」という発想も大事ではないかと思います。
いずれにしても、三セク債の活用は平成25年度中とされていますので、これを活用した土地開発公社の存廃の判断は、時間が限られています。人口減少時代に入り、土地開発公社のあり方やまちづくりについて、正面から検討することが必要な時期になってきているといえます。
謝辞:明石市土地開発公社での検討を通じて、飯塚徹准教授(松本大学松商短期大学部)、山本秀一氏(公認会計士・税理士)の両アドバイザーをはじめ、多くの識者や実務者、明石市土地開発公社の職員のみなさまから知見をいただきました。御礼申し上げます。
アルパックニュースレター171号・目次
新年の挨拶
ひと・まち・地域
きんきょう
- 堺市中区で広がるまちづくりの輪(地縁型とテーマ型の緩やかな融合へ)
/大阪事務所 大阪事務所 岡本壮平・清水紀行・大河内雅司・依藤光代 - 篠山想いがたりプロジェクト~映像を通じてまちのアイデンティティを探る
/大阪事務所 絹原一寛・森岡武 - 第1回まちなみ景観絵てがみコンクールを開催!~絵てがみで見る向日市の魅力~
/京都事務所 山崎裕行・石本幸良
- 国際シンポジウムを開催しました/代表取締役社長 杉原五郎
- 「自ずと成る」まちづくりのススメ/大阪事務所 坂井信行







