アルパックニュースレター171号
『成功する「生ごみ資源化」』ごみ処理コスト・肥料代金激減
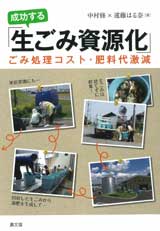
本書は三部構成になっています。「第I部 生ごみ資源化による循環型地域づくり」「第Ⅱ部 全国の自治体の課題分析と資源化の『手法』」「第Ⅲ部 有機物が循環する循環型地域社会の構想」です。中心となる内容は、筆者らが約10年にわたり自治体職員や住民、農業関係者と試行錯誤して作りあげた「生ごみ資源化」の手法です。
「生ごみ資源化」によるまちづくり
本書での「生ごみ資源化」は、従来の生ごみの肥料化やメタンガス等のエネルギー利用のことではありません。「生ごみ」を農業振興、地域経済の活性化、まちづくりなどの有効な「資源」(手法)とすることを意味しています。「生ごみ資源化」のポイントは、筆者らが「社会変換」と定義する2つのことです。
1つは「自然科学的に変換された変換品の経済的価値を高めること」です。「生ごみ資源化」の手法を作ってきた福岡県大木町、築城町では、生ごみからできた肥料を肥料取締法に基づく肥料登録や利用に関する情報提供などを行い、農業者が利用したいと思う商品(肥料)にしています。また、その肥料を利用してできた農産物を特別栽培米やブランド認証、学校給食、地元のレストラン等で利用し、付加価値販売、マーケットの確保に取り組んでいます。ちなみに二町では、生ごみを堆肥ではなく液肥として肥料化しています。液肥は堆肥のように散布の手間がかからない、水田に基肥、追肥として利用できる、さらに、肥料化にあたって、堆肥のような臭いが発生しないメリットがあります。この液肥化も「生ごみ資源化」にあたっての1つのポイントだといえます。
2つ目が「循環の取り組みに誇りをもつ市民の育成」です。すなわち、市民、まち全体を「ごみに対して『処理』の発想から『循環』の発想へ」変換することです。「生ごみの資源化」はハードの施設整備だけでなく、生ごみの分別収集やその肥料で生産された農産物を市民が積極的に購入し、生産者を支えるなど、市民の理解と協力がなければ成立しません。そのためのソフト事業が鍵となります。先ほどの二町では、町内全ての小学生が生ごみ資源化について学習して子どもを通じて親、地域に取り組みへの理解や意識の変化を広げる取り組みをしています。
「生ごみ資源化」の成果
現在、大木町では迷惑施設としてとらえられがちなごみ処理施設がまちの中心部に立地し、循環型社会の学習施設、直売所やレストランを併設した地産地消の拠点施設として、地域の人々が集まる場となっています。築城町では、液肥の活用により農家の肥料代の削減や付加価値のある農産物の販売など農業振興につながっています。
また、「生ごみ資源化」のコスト(運転コストや施設の建設費、住民への普及啓発)は、驚くほど低く、ある自治体ではコスト削減の点から、可燃ごみの処理方法として「生ごみ資源化」に取り組む方針を打ち出しています。
「生ごみ資源化」の普及に向けて
筆者は多くの自治体が「生ごみ資源化」取り組めるよう「自治体有機物研究会(仮称)」を立ち上げ、手法の研究、提案を進めるとしています。ごみ処理コストの増大による自治体財政の逼迫した状況、さらには人口減少、地球全体での資源枯渇や廃棄物問題などの社会環境を踏まえ、今後のごみ処理の1つの方法として「生ごみ資源化」による循環型の地域社会を構築していくことは多くの自治体で検討の余地があるのではないでしょうか。今後、この取り組みがどのように進むのか大変関心のあるところです。
末筆ながら、筆者らをはじめ大木町、築城町は学生時代に大変お世話になりました。現在、このような仕組みができ、地域のみなさんのいきいきとした様子を本当にうれしく思います。
アルパックニュースレター171号・目次
新年の挨拶
ひと・まち・地域
きんきょう
- 堺市中区で広がるまちづくりの輪(地縁型とテーマ型の緩やかな融合へ)
/大阪事務所 大阪事務所 岡本壮平・清水紀行・大河内雅司・依藤光代 - 篠山想いがたりプロジェクト~映像を通じてまちのアイデンティティを探る
/大阪事務所 絹原一寛・森岡武 - 第1回まちなみ景観絵てがみコンクールを開催!~絵てがみで見る向日市の魅力~
/京都事務所 山崎裕行・石本幸良
- 国際シンポジウムを開催しました/代表取締役社長 杉原五郎
- 「自ずと成る」まちづくりのススメ/大阪事務所 坂井信行







