アルパックニュースレター178号
『大災害と法』
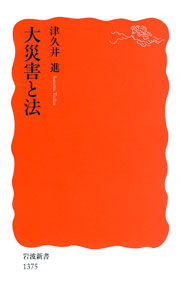
『大災害と法』本表紙
暮らしの視点から法を考える
まちづくりでもっとも重要な視点の一つは、一人ひとりが自分の暮らしとまちがどのように関わっているのかを意識することです。
かつて、夕食の材料は近所のお店に歩いて買いに行きました。最近はロードサイドのスーパーや郊外のショッピングセンターでのまとめ買いに車で出かけるという方も多いのではないでしょうか。その結果、近所のお店は閉店し、新しいスーパーやショッピングセンターは次々とオープンしています。私たちの暮らしのカタチが先か、まちのカタチが先か、ニワトリとタマゴの関係ですが、暮らしの視点でまちを捉えることからまちづくりへのアプローチははじまります。
さて、今回ご紹介する本は、そのタイトルから一般の人には縁遠い法律の専門書であると思われるかもしれません。しかし、本書の冒頭には「被災者の生活目線に立ち、一人ひとりの人間にどのような意味があるのか、という点にこだわって法の役割を紹介しようとした」とあります。私なりの表現で本書を紹介するとこうなります。「この本は、私たちの暮らしの視点から、災害に関わるさまざまな法を紹介したものである」
災害に関わる法
災害に関わる法は主要なものだけでも100 を超えるそうです。建築や都市に関わる法もそうですが、専門家でない一般の人が、すべてを理解するのは絶望的でしょう。一体、法とは誰のためにあるのでしょうか。そこで本書では、3つの「角度」から俯瞰的に紹介することで「法」の役割や意義が立体的に浮かび上がるよう工夫されています。
一つ目は歴史的な流れや制度的な仕組み、二つ目は発災→応急対応→復旧・生活再建→復興→防災・減災という災害サイクルの各段階、そして三つ目は社会の課題との関係です。災害サイクルの中では平常時の備え、社会の課題の中では避難者の支援、原子力災害、個人情報保護、災害対応の担い手といった、先般の東日本大震災でも関心が高まったテーマが取り上げられています。
まちづくりと憲法
ところで、本書の底流にはもうひとつのテーマがあります。それは憲法です。復興の理念は「人間の復興」であり、「憲法が保障する基本的人権を回復すること」であると。つまり復興とは憲法の実現だということです。著者によると、もともと日本国憲法は戦争やその前後に起きた東南海地震や三河地震などの数々の大規模な自然災害からの復興を目指していたのであり、復興という考え方が織り込み済みだそうです。
まちづくりの場面では直接的に憲法を意識することは少ないかもしれません。しかし、復興を具体的に進める行為自体はまちづくりそのものであるし、「個人の尊重」(第13 条)、「健康で文化的な最低限度の生活」(第25 条)、「地方自治の本旨」(第92 条)などはまちづくりの理念そのものでもあります。自分自身のこととして振り返ると、法律家である著者に比べて憲法との間に距離をおいていたかもしれません。
災害復興とまちづくり
本書では関西学院大学災害復興制度研究所がとりまとめた「災害復興基本法」の試案が紹介されています。その中では、復興の目的は「人間の尊厳と生存基盤を確保し、被災地の社会機能を生成、活性化させる」こと、復興の主体は「被災者であり、被災者の自律と基本的人権を保障する」、また地方公共団体は「責務を果たすために必要な諸施策を市民と協働して策定する」とあります。
お気づきでしょうが、「被災地」を「地域」あるいは「まち」と、「被災者」を「市民」あるいは「住民」と言い換えれば「まちづくり基本法」といっても不都合はありません。著者は、阪神・淡路大震災の年に弁護士としての本格的な活動を始められ、さまざまな災害復興の現場に法律家として真摯に向き合ってこられた“市民まちづくり派”とでも言うべき弁護士です。本書を貫く著者の視座は、どこまでもまちづくり的なのです。
アルパックニュースレター178号・目次
ひと・まち・地域
きんきょう
- 芝田2丁目のまちづくりが動き出します~未来都市芝田2丁目協議会の設立&記念イベント「マルシェ」の開催/都市・地域プランニンググループ 清水紀行
- アイ・スポットのイベント報告/都市・地域プランニンググループ 絹原一寛
- 大阪市港区ワークス探検団の取り組み~小学生による中小企業訪問活動/代表取締役会長 杉原五郎
- 第6回CITEまちづくりシンポジウム「大阪をブランディングする~新たな都市魅力を創造し、世界・アジアに発信する~」に参加して/地域再生デザイングループ 中塚一・羽田拓也







