アルパックニュースレター185号
『近居』~少子高齢社会の住まい・地域再生にどう活かすか
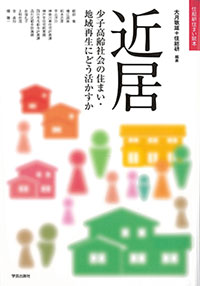
本表紙
みなさんは、自分の親世帯とどのような距離のもと暮らしていますか?
一つ屋根の下で「同居」している方、同じ敷地内やマンション内で「隣居」している方、スープが冷めない距離で「近居」している方、実家から離れた地域で暮らしている方、様々な生活スタイルがあります。
本書は、この中でも「近居」「隣居」というスタイルに着目し、近居に対する子世帯、親世帯それぞれが持つニーズや、近居の効果、近居を促進するために行われている行政施策の紹介等がされています。
本書中でも紹介されている神戸市の「親・子世帯の近居・同居住み替え助成モデル事業」の実施に向けた調査はアルパックがお手伝いしました。その調査の中では、子世帯が近居・同居を選ぶ理由として「安心感」「緊急時のかけつけ」とならび「子育てを手伝ってもらうため」が多くあげられていることや、近居・同居の満足度が非常に高いこと、既にかなりの比率で近居・同居が行われていることなどがわかりました。
本書においても、「近居等」の効果として、「母子家庭や共働き世帯における子育ての手伝い」「高齢の親世帯に対する家事援助・介護」といった福祉的な効果が評価されていると共に、「近居等」の促進により「緩やかな地域定住」「集落コミュニティの維持」といった地域再生に対する効果への期待も指摘されています。
一方で、これまでは一世帯一住宅を基本とした住宅政策が進められてきた背景から、「近居」という居住スタイルについては政策的に扱われてこなかった面があり、その実態を示す統計データも十分ではありません。しかし、人口移動が減少し都市が成熟するに従って、親子関係や地域内定住に注目し、メリットの大きい「近居」という生活スタイルを捉え直す必要があります。
本書においても、複数世帯のネットワークから成り立つ「家族」の住まい方をどのように評価し、住宅政策にどのように反映するのかという視点が今後の住宅政策では必要であると論じられています。また、一方で家族関係から切り離された人たちの存在に対する配慮が必要であるという指摘も重要です。
本書で紹介されている、哲学者ショーペンハウエルの寓話「ヤマアラシのジレンマ」の例えが印象的です。ヤマアラシのカップルは、暖め合おうと互いに近づくと針が刺さり、離れると今度は寒い。互いが傷つかずかつ暖め合える最適距離を見いだすという話です。
前世紀は「同居」がスタンダードであった家族のあり方が、「別居」を基本とした居住スタイルへ変化しました。近年は、「近居」というスタイルによって親世帯・子世帯の最適距離の再構築が進みつつあるように思います。
アルパックニュースレター185号・目次
ひと・まち・地域
- 「生駒らしい景観」の本質に迫る計画づくり~生駒市景観形成基本計画が策定されました/都市・地域プランニンググループ 坂井信行・絹原一寛・依藤光代
- アルパックセミナー 都市における『農地を活かしたまちづくり』~都市と緑・農の共生に向けて~を開催しました(その1)/都市・地域プランニンググループ 岡本壮平・絹原一寛
- 地域の活性化×自分たちも楽しむ仕事=よい仕事?~平成25年度の業務4本から~/地域産業イノベーショングループ 原田弘之・武藤健司
きんきょう
- 生駒に新たな賑わいスポット「ベルテラスいこま」がオープンしました/地域再生デザイングループ 羽田拓也
- 西京銭湯部隊沸いてるんジャーの冊子ができました。
- 新人紹介/都市・地域プランニンググループ 松下藍子・中井翔太







