アルパックニュースレター159号
「クリエイティブ都市論」
~創造性は居心地のよい
場所を求める~
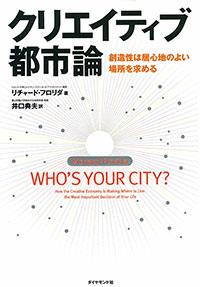
本表紙
<メガリージョン> という言葉をご存知ですか
リチャード・フロリダ(トロント大学教授。創造性を持った人材、すなわちクリエイティブ・クラスが経済の主要な担い手になることを主張)は、「世界はフラットではない、鋭い凹凸があってスパイキーである」という。グローバル化する地球を宇宙の衛星や航空機から眺めると、光量が集中している箇所があり、これこそ、人口が集積し、経済活動が活発に展開され、才能が集まり、イノベーションが盛んなメガリージョンと定義する。
世界には、40ほどのメガリージョン(日本には4つ)があり、そのうちのひとつ広域東京圏は世界で第1位、大阪・名古屋圏は第5位にランクされている。ちなみに、日本の第二のメガリージョンである大阪・名古屋圏には、3600万人が居住し、1.4兆ドルのLRP(夜間光量に基づく地域生産)を産出している。
幸せになれる場所は、どこですか
フロリダは、〈メガリージョンの世紀〉について経済地理学的な視点から独自の分析を披瀝する一方で、〈場所の経済学〉〈場所の心理学〉について語っている。人々は人生の選択において、何を(どのような仕事を)して、誰と(どのような伴侶と)一緒に暮らすか、とともに、どこに住むかという(居住地の選択)を重視している。自分が幸せになれる場所はどこか、これがフロリダの2つ目の問いである。
才能が集まり、イノベーションが活発で、創造性豊かな場所は、芸術家(ボヘミアン)や同性愛者(ゲイ)が住んでいる地域と密接な係わりがあるという興味深い事実を発見する。創造性は居心地のよい場所を求める、というわけである。佐々木雅幸氏(大阪市立大学教授)やチャールズ・ランドリー(コンサルタント、英国)の創造都市論と相通ずるものがある。
いま、日本では、大都市圏を中心に、人口や大学などの都心回帰が進んでいるが、人々は幸せになれる場所を求めて移動しているのだろうか。フロリダの指摘を踏まえて、〈日本における幸せな場所探し〉について考えてみたい。
著作活動のバックヤード(裏庭)
フロリダの本は、都市計画やまちづくりの仕事をしている私達に興味深い事実を突きつけるが、最後の謝辞を読んでいて、この本が生まれるバックヤード(裏庭)にも関心を持った。本書は、長年にわたる地道な取材と調査活動、関連する数多くの文献サーベイ、共同研究者との忌憚のない議論、スタッフとの幅広い協働、家族の精神的な支えなど、ねばり強い努力の積み重ねから産み出されたことを知り、感動し納得した。
最近、山崎豊子さんの本「作家の使命 私の戦後」(新潮社)を読んだ。この本の中で山崎さんは、「不毛地帯」「二つの祖国」「大地の子」「沈まぬ太陽」「運命の人」の舞台裏を語っているが、5年から8年にも及ぶ長期のねばり強い取材活動があって、人々を感動させるベストセラーが生まれることがよくわかった。シンクタンク、コンサルタントも、かくあらねばと痛感した。
アルパックニュースレター159号・目次
新年の挨拶
特集「水辺とまちづくり」
- 水辺のアート発信地“クリエイティブセンター大阪”/代表取締役社長 森脇宏
- 水都大阪2009とうんぱく2009~尼崎運河博覧会/大阪事務所 絹原一寛
- 大阪・天神橋を見下ろす「川辺の暮らし」/大阪事務所 柳井正義







