アルパックニュースレター165号
近況
「きんきょう」をご無沙汰いたしました。ダウンしていたわけではありません。おかげさまで、元気で忙しくしておりました。
行動を列記しますと
昨年下半期の行動を、箇条書きにしますと以下のようになります。あきれるくらい多岐多様もしくは種々雑多です。
(1)6月から8月へかけ、若い諸君の提案・「私の履歴書」4回シリーズ。そのためのアルパック活動史年表制作。
(2)7月:28日、京都府特別参与・井口和起総合資料館長と府庁旧議場の復原計画について協議。
(3)9月:5日アルパックOB会。
(4)10日、BPW(女性経営者・職能人の国際組織)京都クラブでお話。
(5)11日、現役の全社研修会。
(6)19日、京都府庁旧本館応援ネット連続講座パートⅡ開始、通算第4回「京の匠・京人形」。安藤人形店・現代の名工・安藤桂甫さん。
(7)次いで同日、時計台ホールで、京大建築学教室創立90周年記念会。
(8)10月:1日、府庁正庁で、井口和起先生と、旧議場復原計画の第2回協議。
(9)3日、NPO平安京・平城遷都1300年祭平城宮跡会場・平城資料館訪問。
(10)7日から、日本建築家協会(JIA)北九州大会。
(11)17日、応援ネット連続講座第5回「御所と京菓子」。塩芳軒・高家昌明さん。
(12)「京都デザイン賞2010」に「白梅町の家」応募。
(13)なんと「入選」!30日、府庁正庁で表彰式。
(14)11月:6日、地元・桃山南学区社会福祉協議会・自治連合会主催講座。小学校の「ふれあいホール」で「まちづくり」のお話。
(15)9日、金婚記念。娘らのプレゼントで、柊家での休日。
(16)27日、従弟の次男結婚。久しぶりの慶事。リッツ・カールトン大阪に一族集合。
(17)28日、応援ネット連続講座第6回。「禁裏御用・京味噌」本田味噌会長・五代目丹波屋茂助・本田茂さん(実は、前日も会った従兄)
(18)29日、白梅町の家でデザイン賞お祝いの集い。柊家の西村女将さんら18名様。
(19)12月:2日、京都市保育園連盟・保育研究所「保育文化賞」論文審査。
京都商工会議所の職務を交替した杉原社長は、11月に議員に就任。これで私の公的な職務は、ぐんと減ることになるでしょう。
一見雑多な行動ですが、自分ではポリシーを持って動いていたつもりです。その視点からみますと、記念すべき“シークエンス”が浮かび上ってきます。
旧交を温め、いまを語る
(3)(7)(10):OB会・建築教室90周年・JIA北九州大会。いずれでも“長老”の部に入っていることを自覚。久しぶりなのに皆さん“今”を熱っぽく語る。巽和夫先生・
三村浩史先生とは住まい・まちづくり。長谷川義明・前新潟市長とは、NPO仲間の情報交換。
JIAの名誉会員は大会にご招待頂くのですが、海外賓客ご接待のお役目もあります。岐阜の田辺尚美氏・福岡の三島正一氏との旧交。アメリカ建築家協会(AIA)クラーク・マヌス会長ご夫妻、韓国建築家協会(KIRA)イ・サンリム会長ご夫妻とは愉快な新交。
文化財資産の活かし方探求
その会場・西日本工業倶楽部(旧松本邸)は、国の重要文化財。1911年、辰野金吾の設計。アール・ヌーボー風のデザインで、元々迎賓館として建てられています。行政庁舎である京都府庁旧本館とは機能が違います。和洋折衷の庭園も美しく、園遊会に使えます。このような供宴に使われていますので、手入れもよく行き届いています。そこで、(2)(6)(8)(9)の出番。
文化資産を活かすには、当たり前のことですが、お金が掛ります。
そこで得意技・地域計画のセンスで下地を見極め、智恵を加えて味付けします。先ずは得意の「立地を読む」ことから。
京都市役所では、前面の御池通に駐車場公社が経営する地下駐車場があり、来庁者・職員等の駐車をまかなっています。
“車のことがあるのだ“と学び、歴史資産ではありませんが、清水五条の陶磁器協会・展示場では、建築だけでなく、裏にある駐車場の改善を提案しました。立地条件を読んで出入り口を改め、自動化した結果、年間2000万の収入増になり、5年ほどで展示場の建築費を回収できたそうです。
京都府庁の立地は、地下鉄もなく不便だと言われますが、その分、駐車は欠かせません。歴史資産を活かすには、地域計画・建築プラス、ビジネス感覚。
 左から、三村・巽・長谷川の各氏 |
 西日本工業倶楽部 |
ココロとカタチ
昨年の仕事の一つ。京都建築設計監理協会(KSK)で「京都・建築デザインガイド」の出版。
“建築設計論”から始めています。デザインはアートと違って、必ず“機能”を伴い、更に建築は様々なジャンルのデザインとも違いがあります。土地に密着していて容易に動かせない。内部空間があって大きい。造るには多くの人手が掛る。モニュメントやストリートファニチャーは、建築のように見えても、建築とは違います。
内部空間があるのは、人間の様々な生活活動の舞台であるから。そこで、(12)(13)(18)の実践。
「白梅町の家」は、2007年5月に竣工しました。3年半も経っての応募には、ワケがあります。住宅はなによりも暮らし易いことが機能要件。それは住まう人のモチベーション即ち動機と、思い・心情即ちココロ。ココロなんて形になるのかと思われますが、肝心というように欠かせないのです。「白梅町の家」のモチベーションは、建築主・田中峰子さんが、介護なさっているお母さんと、安心して暮らせることです。
思い・心情・ココロは?
十三代冨田屋藤兵衛・田中峰子社長さんの西陣織問屋「冨田屋」本社は“千両ヶ辻”近くのレッキとした町家で、国の重要文化財に指定されています。
田中峰子さんのブログ「心の日記」に、四季の情景とともに詠まれている、祖先から受け継ぎ、未来へ伝えようとするココロを感じて頂けるでしょう。
ココロをカタチに表現すると、こうなったのです。見たところ、この自邸は本社屋とは全く対照的です。瓦・障子・襖・畳はありません。ところがご覧になって「桂離宮」だと感じられるのです。
雁行高床にガラスの月見台、プロポーションにお感じになるのでしょう。引手や釘隠の代わりに、オーナメントが置かれます。
普段の暮らしは、雁行の東棟だけですみ、西棟はゲストのためのハレの空間。桂離宮と違って今様なのは夜景。照明です。そこで、峰子さんの和服姿がすてきに映えるのです。
3年半待ったのは、快適に使えているか、確かめる時間でした。
建築であれ、まちであれ、ココロをカタチに実現するのが、我われの仕事です。
 雁行高床:手前東棟・奥・西棟 |
 西棟サロンとガラスの月見台夜景 |

雁行高床:桂離宮御殿
イノチを育てる協働
保育文化賞は第8回になりました。(19)。今回は8編。論文・報告の審査で“感動”を頂きます。
近年「発達の気になる子ども」が多くなっていると言われています。軽度発達障害の原因は、家庭でのしつけ、遺伝子、環境ホルモンの影響など諸説ありますが、総数が増えているとは思えません。
昔から「活発なお嬢ちゃんですね」とか「ちょっと変わったお子さん」はありました。人間は精密機械かクローンのように作られるわけではなく、“ゆらぎ”ながら成長するものだと思います。大人になってもゆらいでいます。「変人」も「宇宙人」もいます。社会的認知が高まり、受診が増え、スクリーニングの精度・手法が発達したことが大きいでしょう。
しかし、早産の超低体重児では疾患・障害の可能性が高くなります。
NICU(新生児集中管理室)で育ち、既往歴のある乳児を引き受けようと決断される保育園の園長さんに先ず、感激します。落ち込むお母さんは、それでも我が子は可愛い。障害を認めたくないお父さんもいます。園は保健士を通じて児童相談所にアドバイスを求め、乳児院・整肢園と連携して言語聴覚・発達遅滞等の専門的診断を受け、懸命の連携・リレー、関係施設の担当者とのミーティングなど大奮闘。いきいき地域療育支援事業、障害児・保育者1対1の加配制度の民間園への適用などの施策をタイムリーに打ち、支援する市の担当者。担当保育士と園外の機関との連携を指揮する主任保育士。子育て現場は、日々闘いです。
このような記録は、ご両親からその子に伝えて上げてほしいと思います。未熟で生まれ、或いは障害を越えて、科学者や芸術家として立派に社会に貢献されている人は内外にたくさんおられます。
もし、園長がリスクを恐れて受け入れを断り、主任保育士が、面倒な連携プレーを指揮する器量を持っていなかったら、もし行政担当者が、業績に表れないと、1対1加配制度の適用をためらっていたらその超低体重児はどうなったでしょう。
学んだことを伝え、教える
昨今、企業でも学校でも進んでいる「業績評価」はクセモノです。個人の実績主義に陥り、職場がバラバラになる恐れがあります。政策や制度設計は、たいへん責任の重い仕事です。アルパックの「現地主義・総合主義・実証主義」は、創業の時、すぐに役立たない哲学学習を重ねて到達した原理・原則です。「評価制度を評価する」ことと哲学論争が不可欠です。
「研修会」なるものもクセモノだと思っています。
「私の履歴書・シリーズ」(1)は、具体的なエピソード方式を採りました。府庁旧本館連続講座(6)(11)(17)とは、関係があります。
老舗と呼ばれる伝統文化型のお商売は、あまたありますが、今回3講座の主役の業態はいずれも“製造・販売”です。即ち、基礎はテクノロジーで、セールスとの組み併せで、それぞれの労働に応じて身につけるべき技術や知識があること、経営体の規模が大きくても、基本は変わらないものです。
教え、伝える「研修」は具体的・実践的でなければならないと考えています。実際に働いて、技術と知識が「智恵」に到っている方から教え、伝えて頂くのが一番です。
府庁旧本館の講座は、若い人に来て頂きたいと日曜日に設定しているのですが、高齢者と若い女性に2分化しています。
「禁裏御用・京味噌」の本田は、私の総本家。中小企業のスピリットは、一家が力を合わせて、働くこと。私も4~5歳の頃から手伝っていました。味噌樽洗いでした。子どもは小さいからタルの中へ入れられて、ササラで隅を洗うのです。夏は冷水、冬はお湯で、水遊びのようですが。
本田茂さんが紹介した本田家の家訓の第3「家の子は宝なり。慈しみ、育むべし」即ち、従業員第一。極めて具体的でして、祖父は「夜学」と称して、丁稚・手代衆に、読み書きそろばんから、論語や史書を教えていました。祖母は女中衆に、自分自身が宮家屋敷で教わった行儀・作法から料理・裁縫まで教えていました。人ごとではなく、地域での仕事はしたこともないのに、まちづくりを語るコンサルタント。ソロバンも出来なければ、実践と学習で身に付けた「経営者観」もあやふやな経営者。等々。このような陥穽に落ちないよう「研修」に気をつけましょう。心情にはじまり、科学に到る地元でまちづくりを語るのは、地域計画屋として冥利に尽きます。とともに、地域に足を着けているか、真価が問われます。それだけに、(14)の講座は、準備に意外に時間を費やしました。
会場は桃山南小学校の「ふれあいホール」80人ほど入れます。まことにけっこうな舞台です。お客さんがよろしい。お菓子屋のおじさん、豆腐屋のおばちゃん、それにここは大学の名誉教授、大会社の元社長さんなど、偉い方も多くお住まいです。
実は、桃山南は、ふるさと回帰なのです。東京オリンピックの前年・1963年に東京から帰って移り住んで47年。その13年前、即ち60年前に、京阪電鉄宇治線で黄檗の京大宇治分校へ通っていました。しかし、桃山南口の駅には、一度も降りたことがありませんでした。沿線は美しく刈り込まれたお茶畑でしたが、ここは荒涼として魅力がなかったです。農地が広がり、宇治火薬製造所木幡分工場の建屋が残っていました。1937年に“西山夘三少尉”が設計された工場でした。
皆さん、誰でも自分が住んでいる所に誇りを持ちたいものです。そのために、その場所のイワレを知り自慢したいものです。そこをより良くして行こうと行動すれば立派な「まちづくり」です。
イワレを知るとは、地理と歴史から始まるのが定石。
ミズとナマズとの付き合い
この学区域の地形は三角形をしていまして、三辺を川―宇治川・山科川・堂ノ川(木幡池)で囲まれ、面積は約1平方キロ(100ha)、平坦で山も丘もありません。
いや「山」が一つあります。小学校の中庭に子どもたちが造った「桃山・みなみアルプス」。高さ2メートル。
近世、天下人・秀吉が伏見城を建て、堤防(太閤堤)を築くまでは水の下でした。そして、前世紀半ばまで、定住人口ゼロ。それが今では、9000人。市内で指折りの「良好な住宅地」です。
最初の開拓者は、1957年、日本住宅公団桃山団地・中層とテラスハウス18棟176戸。続いて西隣に京阪電鉄の分譲宅地。1963年、東部に京都市の住宅公社が分譲住宅の開発を始めました。京セラの稲盛和夫さんもここにお住いでした。
その頃、地域で一番元気なのは、団地の住民でした。30~40歳代が多数で、ふところ具合も同じです。子どもがいっぱい。団地で運動会をやっていました。
驚いたのは、2年後の1965年9月。台風24号で宇治川氾濫。元の水の底になってしまいました。団地自治会はボートを備え、水防団を組織しました。
以後、排水機場、排水樋門が次々と整備され、水没することはなくなりましたが、ボートも水防団もなくなり、水との付き合い方も忘れてしまいました。京都市のハザードマップでは、東海豪雨(2000年9月)規模の大雨で全域床上0.5~3.0の浸水。
秀吉が隠居所として建て始めた指月山伏見城は、慶長大地震で崩れました。推定マグニチュード7.5。ハザードマップは花折断層の活動を想定していますが、地震研究は起こってから進歩するもの。判っていない断層が、潜んでいると考えておくべきです。
とにかく、地域の安全は、地域の歴史を知ることからです。
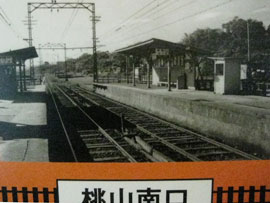 1950年代の駅(京阪トレインミュージアム) |
 1960年代:団地の運動会 |
まちはすべて文化資産
隣の桃山東学区域になりますが、すぐ北に、伏見城船入跡があります。1965年頃に埋め立てられて住宅やマンションが建っていて、NPO伏見楽舎が検証して標識を立てています。
家康の孫・千姫は、伏見城の徳川屋敷で生まれ、慶長8年(1603年)ここから船に乗り、大坂城の豊臣秀頼のもとへ輿入れしました。7歳でした。
因みに、家康・秀忠・家光3代は、伏見城で将軍の宣下を受けていますし、家康は駿府城より伏見城に居た方が永かったそうです。江戸時代の初め20年は「伏見時代」と言ってもよいのではないでしょうか。
遡って、平安期、源氏物語宇治十帖を読むと、都人は夜明け前に後世の鳥羽殿あたりから船に乗り、指月と呼ばれていたこのあたりは朝もやの中を宇治へ通っていたのです。まちはまるごと文化的資産と言ってよいでしょう。
桃山団地は、地域文化資産の第1号です。独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)の立場からは、何百件もの賃貸住宅ストック再生・再編の一つで、類型として用途転換に仕分けして、事業化することになるのでしょうが、地元の心情では、桃山南地域のパイオニアです。おしゃれな若者・高齢者のためのシェアー・ハウスになれば、地域再生になるでしょう。
ここには、その心情のシンボルツリーがあります。ビャクシン(伊吹)が3本。京都府庁旧本館の前にもあります。成長の遅い木で、樹齢300年にはなるでしょう。
URさんには、何故これを植えたか、イワレは伝わっていないかもしれませんが、職人は敬意を表して美しく剪定しています。因みに、その向こうに見える4号棟には、ノーベル物理学賞の益川敏英さんがお住いでした。
ぼつぼつ、私自身も“メモリアル”に分類されるようになってきました。

桃山団地のビャクシン
アルパックニュースレター165号・目次
新年の挨拶
ひと・まち・地域
- 低炭素都市づくり異なる2つの地域より/大阪事務所 畑中直樹・中川貴美子
- 学校給食からひろげる地産地消~食育推進計画における政策指標を切り口に
/京都事務所 廣部出・大阪事務所 原田弘之・渡邊美穂 - 命を救うプロジェクト~心臓疾患術前シミュレータの開発/京都事務所 高野隆嗣
- キッズバーベキュー高浜楽校を開催/大阪事務所 高田剛司







