アルパックニュースレター182号
フォーラム「関西の食文化とフードツーリズム」が開催されました
みなさんは、旅行に行ったときに、その土地のおいしいものが食べられることを楽しみの一つとして期待しませんか?
観光目的が多様化してきていると言われて久しいですが、食についても、楽しみの「一つ」ではなく、食そのものが目的化されている観光が増えてきています。確かに、従来から「いちご狩り体験ツアー」や「かにかにエクスプレスツアー」といった類いの旅行商品はありましたが、最近では、ワイナリーをめぐったり、B級ご当地グルメで有名になったまちに出かけてみたり、農家レストランや古民家カフェでの食事を目的にふらりと旅行に行くことが増えてきていると思われます。
そこでは、美味しさの追求はもちろん、食材の生産地に出かけることによって、その土地の自然や景観を楽しみ、生産者・料理人との交流が生まれ、総合的に「食」を楽しむ観光が成立するのです。
このフードツーリズムについて、おそらく日本で初めてのフォーラムとなる「関西の食文化とフードツーリズム」が9月14日(土)、大阪府立大学I-siteなんばで開催されました。主催は、私もメンバーになっている「フードツーリズム研究会」(主宰:尾家建生氏・山川雅行氏、事務局:大阪観光大学)です。
フォーラムは、尾家先生の基調報告「フードツーリズムの現状と課題」からスタートし、山形県の庄内から特別ゲストとしてお招きした、奥田政行オーナーシェフ(アル・ケッチァーノ)に、「料理が地方を元気にする」をテーマにしたお話を頂きました。
また、大阪の河内でワインツーリズムに取り組むカタシモワインフード(株)の髙井利洋社長、農家レストランで地域活性化に取り組む奈良県職員の福野博昭さんを交えて、パネルディスカッション「関西からフードツーリズムを広めよう」が行われ、会場110名の参加者と一緒に議論が盛り上がりました。
このフォーラムを通じて、私が再認識したことを一つだけ挙げるなら、フードツーリズムは、旅行者の楽しみを広げるだけでなく、その土地で一次産品や加工品を生産する人々にとって、気持ち的にも経済的にも元気にさせる役割があることです。そして、地元食材を理解し、使いこなせる料理人の存在が鍵であることも実感しました。
感想をお聞きしたら、参加者の皆さんも非常に満足されたフォーラムになったようです。当日は、研究会で作成した「関西フードツーリズムMAP」を配布し、「フードツーリズム宣言」も発表しました。残念ながらこの紙面では紹介しきれませんので、フォーラムの様子については、フードツーリズム研究会のHPをご覧ください。フードツーリズムマップもこのHPからダウンロードできます。
http://www.foodtourism.jp/
<フードツーリズム宣言>
1.フードツーリズムは、地域ならではの料理を味わうことを求める観光形態であり、土地の味覚を通じて、歴史や文化、景色なども体験し、地域の人々のライフスタイルにふれる旅行スタイルです。
2.フードツーリズムは、観光と味覚の成熟から生まれた新しい観光、ニューツーリズムです。
3.フードツーリズムは、地域にとってその土地の食材と調理による美味しい料理を旅行者に提供することにより、地域の良さを再認識することにつながります。また、このことを通じて、地域経済の活性化にも貢献できます。
4.フードツーリズムは、都市と地方の暮らしを相互に豊かにします。
私たちはフードツーリズムをさらに広め、地域の振興につなげていきたいと思います。そのため、フードツーリズムの情報収集と情報発信に努めます。
5.フードツーリズムを全国に広め、日本の食文化を高め、魅力ある観光立国日本を目指しましょう。
平成25年9月14日 フードツーリズム研究会
 フォーラムの様子 |
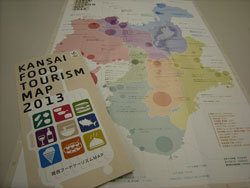 関西フードツーリズムMAP |
アルパックニュースレター182号・目次
寄稿
ひと・まち・地域
きんきょう
- 上野千鶴子氏との公開対談をしました/竹井隆人 (政治学者、アルパック顧問、(株)都市ガバナンス研究所代表)
- 授産所の新しい仕事!周藤さん、遠征して先生になる!/公共マネジメントグループ 廣部出
- フォーラム「関西の食文化とフードツーリズム」が開催されました/公共マネジメントグループ高田剛司
- きっかけは、地域自慢を見直すこと/地域再生デザイングループ 森岡武
- エネルギーシフトと地域づくりを訪ねる旅/代表取締役会長 杉原五郎
- アルパックの経営理念を策定し、イメージロゴも作成しました/代表取締役社長 森脇宏







