アルパックニュースレター162号
西宮市民が考える「暮らしとまちのビジョン(案)」~西宮市都市計画マスタープランの取り組み
普段の暮らしから自分とまちとの関わりを考える
現在、西宮市では都市計画マスタープランの見直しに取り組んでいます。(Vol.158に関連記事あり)
今回の見直し作業の特徴は、「西宮まちづくり塾(Vol.158参照)」や「まちづくりワークショップ」といった積極的な「市民参加プログラム」を取り入れているところです。
「西宮まちづくり塾」では、景観や交通と言ったテーマごとに具体的な事例を交えながら、私達の暮らしがまちづくりとどのように関わっているのかを学びました。
それを踏まえ、「まちづくりワークショップ」では、参加者一人ひとりが「私達は普段、どのようにまちと関わっているのか」「私達は西宮でどのような暮らしをしたいと考えているのか」を確認しながら、西宮市の将来像となる「暮らしとまちのビジョン(案)」をとりまとめました。
意見の共有化
この作業において最も重視されたのは、「異なる思いや価値観の共有化を図る」という点です。
最初はお互いの話を懐疑的、否定的に聞いていた人も回を重ねるにつれ、納得できる部分や共感できる部分を発見し、最後にようやく思いを共有するに至りました。
その結果、とりまとめられた6グループの「暮らしとまちのビジョン(案)」の根底には、“つながりの大切さ”や“相互理解の大切さ”といったことが共通部分として盛り込まれていました。
 |
 |
市民がビジョン(案)発表に込めたメッセージ
「暮らしとまちのビジョン(案)」は、庁内の全局長を招いた公開発表会で報告されました。
今回の「暮らしとまちのビジョン(案)」は都市計画だけに特化した内容ではありません。子育て、地域福祉、環境・・・など多様な視点から“暮らしとまち”を見つめてとりまとめられています。そのため、今回の発表には「私達は西宮市をこんな風にしたいと考えました。出来ることは自分達でやります。でも私達だけで出来ないこともたくさん言いました。その部分は市全体で受け止めて下さい。」というメッセージが込められていたと思います。
 |
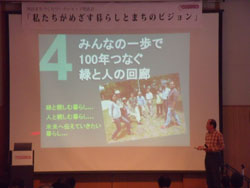 |
市民と行政の思いでつくる都市計画マスタープラン
この「暮らしとまちのビジョン(案)」はワークショップに参加した市民が共有できる将来像として取りまとめています。しかし、それだけで市の将来像と呼べるわけではありません。今度はそこに行政の思いを注入し、すりあわせる作業を行ってはじめて市全体の将来像として都市計画マスタープランに位置づけられるはずです。今後、この作業はワークショップに参加した6グループの代表者(6名)と学識者(6名)で構成される策定委員会を中心に行われます。
どのようなビジョン、どのような都市計画マスタープランが出来あがるのか・・・来年の春頃にはその全容を御報告できる予定です。
アルパックニュースレター162号・目次
特集「農村とまちづくり」
- マチとムラとの新しいつながりのカタチをつくる!-堺市と奈良県東吉野村との広域連携-/大阪事務所 原田弘之
- 農村の景観保全に取り組む~景観農業振興地域整備計画モデル地 区の検討~/大阪事務所 森岡武・絹原一寛
- 伊賀の菜種油「七の花」が本格生産を始めます/大阪事務所 高坂憲治
- 地域住民で守る農村コンビニ「(NPO)耶馬渓ノーソンくらぶ」/九州事務所 山田龍雄
- 人材育成講座によるグリーンツーリズムの推進/京都事務所 江藤慎介
ひと・まち・地域
きんきょう
- 西宮市民が考える「暮らしとまちのビジョン(案)」~西宮市都市計画マスタープランの取り組み/大阪事務所 清水紀行
- 大都市圏まちづくりフォーラムを開催しました/代表取締役社長 杉原五郎
- 第44期株主総会を開催しました/代表取締役社長 杉原五郎







