アルパックニュースレター169号
既成市街地における土地利用マネジメント
~潮江密集地区のまちづくりの事例
はじめに
これまで、既成市街地の更新については、老朽建築物の除却により公共施設整備と良質な建築物の整備を一体的に行う土地区画整理事業や市街地再開発事業などが効果的とされてきました。
密集市街地においても、全面的なクリアランスによって、駅前広場や大規模商業施設の整備、共同住宅化の推進などによって、まちとしての防災性と利便性の向上を図ってきました。
しかし、実際は権利者合意の困難さ、それに伴う事業期間の長期化、また事業完了後においても、期待通りの機能導入が図られないなどの問題が山積しています。さらに近年は、行政の財政的制約の問題などもあって、事業実施そのものへの抵抗感も少なくありません。
このような状況下にあって、いかに既成市街地の更新、とりわけ密集市街地の防災性の向上を図っていくべきかについて、業務での携わった事例をもとに考えていきたいと思います。
尼崎市潮江地区
尼崎市潮江地区は、JR尼崎駅の北側に位置する昔からの住宅地です。駅近で買物施設も多数立地する非常に利便性の高い環境に恵まれています。
しかし、地域内は狭隘な道路がいりくみ、狭小な敷地が多いことなどが相まって、老朽化した木造建築が多数占める住宅地となっています。そして、平成15年に行われた国土交通省の調査の結果、「地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地」(重点密集市街地)として位置づけられることとなりました。
このような状況のなか、地域住民はまちづくり協議会を立ち上げ、住民参加による「安全・安心・快適に住み続けられるまちづくり」の実現に向けて取り組みはじめました。
ハードとソフトの両面から誘導する
前述したように、密集市街地の解消に向けては、住宅の共同化(マンション化)、道路や公園の基盤整備等による方法が、一見すると早期実現が可能で効果的な印象があります。しかし、それはひとつの手段に過ぎません。実際は事業実施に至るまでの合意形成の困難さをはじめ、長きにわたる時間を要し遅々として進まないという現状があります。
当地区南側のアルパックが一部担当した市街地再開発事業(アミング潮江等)についても、事業認可から事業完了まではおおよそ10年近くの歳月を要しています。
また、このような事業を通して災害に強いハードな意味でのまちは実現されるかもしれませんが、古くから築かれてきた地域コミュニティ等が断ち切られ、ソフトな意味でのまちが瓦解してしまったという意見も聞こえてきます。
潮江地区では、そういう声に耳を傾け、「現在の住民の暮らしやそれを支える地域のつながり」を第一に考えた方法が必要だと考えました。
現在、接道条件を満たしていない敷地については、新築・建替え時には確実に4m道路が確保されます。しかし、潮江地区では「地区計画」でさらに50cmの追加の壁面後退(場所によってはそれ以下もありえる)を定めることで最低5m以上の公共的(道路状)空間の確保に努めることとしました。さらに、建築構造についても「準耐火建築物」以上という制限を設けることで、ハード面での防災性能向上に取り組んでいます。一方で、これら地区計画への適合が認められた場合は、建築規制の緩和(斜線制限や前面道路による容積率制限)を設けることで建替えを誘導する方策も設けています。
また、ソフト面では、「暮らしの作法」という地域の自主ルールを定め、日々の暮らしのなかでの「お互いさまの関係」を意識した取り組みも行います。
このように、直接的な都市基盤整備を行うことなく、「地区計画」による建替え時等のルールと暮らしの中での配慮やマナーを定めた「暮らしの作法」を両輪とするまちづくり計画により、ハードとソフトの両面から防災性能の高いまちづくりのマネジメントに取り組むこととしたのです。
 地区計画図 |
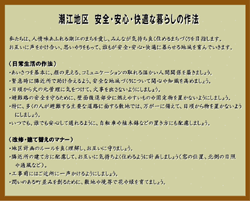 暮らしの作法 |
住民参加を通した意識の醸成
まちづくり計画(地区計画+暮らしの作法)の作成に向けては、「住民意向調査」や「防災まちづくり勉強会」等を通しての地域の問題・課題の洗い出しにはじまり、地域住民による「空き家・空き地の実態調査」など、住民参加を第一とする多岐にわたる取り組みが行われました。
その結果、地域の問題・課題・暮らしのイメージの共有化、地域住民(権利者含む)のまちづくり意識の醸成、さらにまちづくり計画の作成へとつながっていったと思います。
一歩ずつ着実に進める災害に強いまちづくり
今後、潮江地区では、「地区計画に即した防災性の高いまちへの整備・誘導を」、「暮らしの作法という日々の地道な取り組みで安全・安心な生活空間の確保と隣近所の関係性の構築」に取り組んでいきます。まさに住民一人ひとりが一歩ずつ着実に災害に強いまちづくりの実現を目指します。
3月11日の東日本大震災により、地震災害は常に私たちの暮らしと隣り合わせにあることが再認識されました。今回、潮江地区で採用した方法では、今すぐにまちの姿が劇的に変わるものでもなく、まちの防災性が高まるものでもありません。そのため、「早期に根本的な基盤整備からまちの防災性を高めるべき」という声が上がるかもしれません。その事は決して否定されるものではありません。しかし、成熟(硬直)化した既成市街地において、何が優先的に求められているのかを今一度考えるべきときが訪れているように思われます。
潮江地区では、「地域住民の自主性や共助の関係性」といったものを何より重視し、その観点から対応策を考えました。ここに、既成市街地における今後の土地利用マネジメントのひとつの方向性が示唆されているのではないでしょうか。
10年、20年後に潮江地区が、誰もが安心して暮らせるまちとなっていることを期待しつつ、その動向を見守りたいと思います。
 地区の危険箇所や避難路等を確認する勉強会 |
 まちの問題・課題を抽出し、一覧化したマップ |
アルパックニュースレター169号・目次
「まちづくりとエリアマネジメント」
- 名古屋における協議会型まちづくりの紹介~広がり始めたエリアマネジメント
/名古屋事務所 尾関利勝 - 既成市街地における土地利用マネジメント~潮江密集地区のまちづくりの事例
/大阪事務所 岡本壮平・清水紀行 - 周辺市街地の土地利用マネジメント~非建築的土地利用の“状態”のコントロール
/大阪事務所 絹原一寛 - 地方都市の生活拠点のマネジメント~持続的な生活圏構造に向けて/大阪事務所 岡本壮平
- 住宅地の住環境マネジメント/大阪事務所 嶋崎雅嘉
- まちなかバルによるエリアマネジメントの第一歩/大阪事務所 中塚一
ひと・まち・地域
きんきょう
- 文化的転換/相談役(NPO平安京 代表理事)三輪泰司
- 「スマート・シュリンキングによる関西再生」まちづくり技術交流部会に参加しています
/京都事務所 石川聡史 大阪事務所 中塚一・絹原一寛・橋本晋輔 - 守山市でベンガラ塗りワークショップをしました/京都事務所 三浦健史







