アルパックニュースレター169号
復刻版「これからのすまい」―住様式の話―
NPO法人西山夘三記念すまい・まちづくり文庫が、西山夘三生誕百年記念事業として復刻版を、原著と同じ相模書房から出版しました。
中学生だった
原著が出版されたのは、1947年(昭和22年)9月、あの大戦が終わって僅か2年後でした。近くの本屋さんで買いました。当時、旧制中学校の4年生・16歳でした。ひらがなの題名と装丁、イラストに惹かれたのです。西山夘三という人も、建築のことも全く知りませんでした。
それから5年後、1952年(昭和27年)7月。大学の3回生・21歳になっていて、熊野灘沿岸漁村調査に参加していました。尾鷲から小さい船に乗って或る漁港に着きました。何処から聞いて来られたのか、小学校の女の先生が「西山先生にサインをお願いしたいのですが」と、「これからのすまい」を差し出されました。私の初版本は、友人に貸してそのまま返ってきませんでした。彼は文学部の学生でした。
つまり、「これからのすまい」を買い、愛読していたのは、住宅建築の専門家でも、研究者でもなく、素人であり、日本の庶民大衆だったのです。
西山夘三は、1944年(昭和19年)に「国民住居論攻」を出版しています。これは、表題のように漢字が多く、おそろしく難解な本です。1948年毎日出版文化賞受賞。復刻版に使われたのは1952年の11版です。1版3,000部として33,000部になります。定価280円です。最終的にはどれくらい出たでしょう。
個人で「助教授」でも出来ることは著作・学会活動。52年、建築学会支部評議員、59年、副会長。60年、日本学術会議第5期議員に当選。業績にプラス知名度は、抜群に上っていました。学術会議議員の西山夘三が、京都大学教授に昇格されたのは、翌1961年・50歳でした。
特技の「絵」も活かされていました。「ああ楼台の花に酔う」(1982年・筑摩書房刊)は三高寮生活を描いたマンガ。本社に「紅燃ゆる」を刻んでおられた河野卓男ムーンバット社長は、関経連副会長でしたが、100部買って経営者仲間へ贈っておられました。
方法論
本著の目的は、冒頭で言っています。「我々の眼前には住まいに関聯して解決すべき問題が山積している。・・・・・・新しい住まい様式と新しい国民住居標準の諸問題は、いずれも我々の果敢な解決を待っている。」 西山夘三の方法論は、住宅を「住居空間」と「住まい方」の関係、即ち、物的な地域・場所・空間と、中味である使い方・住まい様式・住生活発展過程との対応関係で捉えることにあります。これは市民・国民の生命・安全、経済・事業の新しい発展のために、病院建築と医療活動、港湾空間と流通活動、お店の立地と商いの仕方、そして、都市空間と都市生活との間にも山積している矛盾解決の方法に通じます。
もう一つは、研究プロジェクト方式です。大学の目的は教育・研究。漁村・農村調査もそうですが、香里団地、万博会場計画もプロジェクト。アルパックは企業経営体ですから、地域プロジェクトの目的はビジネスと人材育成になります。しかし、一つのプロジェクトで、育つ研究者や技術者は、せいぜい1~3人くらいです。本人の問題意識・感性、或いはヤル気に掛っています。
経営感覚
地域には我々が果敢に挑戦し、プロジェクトを組み、解決すべき矛盾・問題が山積しています。経営者でござい、総務部長でございと称していても、実際に修練を積むのは難しいものです。経営学の本を読んだり、セミナーに参加するのもよろしいが、実は、学習のネタは身近にあります。買って頂く方、読んで頂くのは誰か。商店街のお店の方、中小零細企業の方の胸に響くか。そのようなことに気がつくかどうかは、本人の感覚、或いは意欲の問題です。
「これからのすまい」は、アルパックの方法論の原点であり、経営感覚を磨き、ビジネスを築くためのものすごいテキストでもありました。
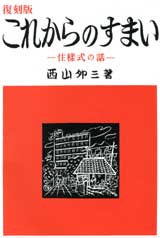
本表紙
アルパックニュースレター169号・目次
「まちづくりとエリアマネジメント」
- 名古屋における協議会型まちづくりの紹介~広がり始めたエリアマネジメント
/名古屋事務所 尾関利勝 - 既成市街地における土地利用マネジメント~潮江密集地区のまちづくりの事例
/大阪事務所 岡本壮平・清水紀行 - 周辺市街地の土地利用マネジメント~非建築的土地利用の“状態”のコントロール
/大阪事務所 絹原一寛 - 地方都市の生活拠点のマネジメント~持続的な生活圏構造に向けて/大阪事務所 岡本壮平
- 住宅地の住環境マネジメント/大阪事務所 嶋崎雅嘉
- まちなかバルによるエリアマネジメントの第一歩/大阪事務所 中塚一
ひと・まち・地域
きんきょう
- 文化的転換/相談役(NPO平安京 代表理事)三輪泰司
- 「スマート・シュリンキングによる関西再生」まちづくり技術交流部会に参加しています
/京都事務所 石川聡史 大阪事務所 中塚一・絹原一寛・橋本晋輔 - 守山市でベンガラ塗りワークショップをしました/京都事務所 三浦健史







