アルパックニュースレター169号
地方都市の生活拠点のマネジメント
~持続的な生活圏構造に向けて~
人口減少社会を迎え、人口の都心回帰現象が進む中、大都市や地方中核都市では当面人口増加が見込まれる一方、その周辺にある地方小都市、特に中山間地域や辺地を抱える地方都市では、人口減少が激しく地域生活の維持そのものへの不安が大きくなっています。
ここでは、中山間地域での業務経験から、人口減少に直面する地方都市における生活機能の維持・マネジメントについて私見を述べます。
地方都市における生活機能にかかる問題
地方都市では、程度の差はあるものの、生活機能の維持について、次のような問題を抱えていると考えられます。
◆自動車依存の先にある不安
自動車に依存した生活様式が普及しており、中心部の商業集積地に人(車)が集中する一方で、旧来からの商店街等は衰退が著しく、自動車に乗れない人を中心に日常生活上の不安が増している。
◆生活機能の“内憂外患”
高速交通網や幹線道路網の整備がストロー効果をもたらし、周辺都市に購買力が流出する。それに対抗するため中心部の機能を強化すると、かえって小規模店の撤退など地区レベルの利便性が損なわれるというジレンマ。
◆効率化の光と陰
市町村合併を契機に、効率化の観点から、立地や地形等の条件不利地から順に、小学校の統廃合、店舗やサービス施設の撤退、バス便減少…それらが重なって地域の利便性を損ない、さらに若年層の流出を助長し、旧町中心部などの生活機能の空洞化が進行。
地方都市に共通するのは、市町村合併後の都市づくりにおいて、最小単位は地区・集落、最大は市町村区域として、その中間領域にあたる「地域」をどのように捉え、その「生活拠点」をどのように配置し、生活利便機能をどのように確保していくか、という課題です。もちろん、都市中心部との関係や背後にある集落地との関係、あるいは周辺都市との関係など、都市特性に応じて考慮する必要があります。
「地域」の設定と「生活拠点」の維持に向けて
(1)生活圏の階層化
まず、日常生活行動や歴史的経緯、その他地域特性などを考慮して、市町村内外にわたる生活圏域を階層化することが重要です。この際、感覚的ではありますが、住民が「自分のまちだ」と感じられる範囲、つまりコミュニティの広がりを重視することが重要です。身近な暮らしの場である地区・集落を基本単位とし、旧町単位ぐらいを一次生活圏、それらの集合体として市町村域を二次生活圏として設定するのが適切であると考えます。
(2)生活拠点の計画化
「地区・集落」は居住機能が主であり、地域で支え合うコミュニティの育成に官民協働で取り組むことが重要です。その上で旧町中心部などを「生活拠点」として、日常生活に必要な機能-『店舗、診療所、郵便や金融(ATM)、子育てや介護など公益施設、公民館や行政窓口など公共施設』-などをコンパクトに確保します。より高次な都市機能(全市に1つあればよい機能)は市町村の「中心拠点」に確保します。ここで、「地区・集落」と「中心拠点」は場所も機能も明確ですが、「生活拠点」の配置・機能は流動的であり、総合計画や都市計画マスタープラン等にきちんと位置づけることが望まれます。
(3)地域交通の一体的確保
上記(1)(2)による生活圏の階層化に対応する形で高齢社会の暮らしを支える「地域交通」のあり方を一体的に計画することが望まれます。例えば、中心拠点と生活拠点間は基幹交通(路線バスやコミュニティバス等)、生活拠点から集落群までは地域交通(デマンドバス等)に区分して、運行事業者や車両・サービス水準などにメリハリをつけることで、システム全体としての効率化を図る考え方が必要になります。特に末端部になるほど事業上厳しくなるので、自主運行バスなど地域住民やNPO等の参加・連携を考慮する必要が生じてきます。
(4)行政計画への位置づけ
上記の内容を担保するため、都市・地域の将来構造、生活拠点の都市機能や土地利用計画、交通体系計画など、まちづくり計画として位置づけることが望まれます。お手伝いしている自治体では、都市計画マスタープランの中で方向付けを行っています。
生活機能マネジメントの鍵は「新たな公」の実践!?
行政計画に位置づけたものを「画餅」に終わらぬよう施策・事業に取り組んでいくことが必要です。
生活拠点の機能の内、公共公益サービス機能はある程度行政的な立地コントロールが可能ですが、店舗や地域交通など民間サービス機能については市場性が強く影響します。そのため、地域の人々の物心両面からの支え、つまり「地域の機能を愛し使うこと」が必須であり、行政に頼るだけでなく、住民自らが自分たちの暮らしを支える機能として、その維持に協力していく姿勢が求められます。
全国的には、住民自らが出資者となりコミュニティ・ビジネスとして、ガソリンスタンドやコンビニ店を経営する集落などの事例も出てきています。住民自らが地域で経済を循環し、少しでも雇用を生み出し、若者の働く場にするような野心的な取組へと発展させることも決して夢ではありません。まさに、「新たな公」の考え方のもと、地域自らの問題として生活機能維持に関わること(=マネジメント)こそが、人口減少下においても地域での暮らしを豊かに持続していくための処方箋の一つであると思います。
中山間地域は人口減少社会のトップランナーとも言われます。幅広い視野から土地利用+αのマネジメントを重視して、こうした地域の都市・地域づくりに関わり、応援していきたいと思います。
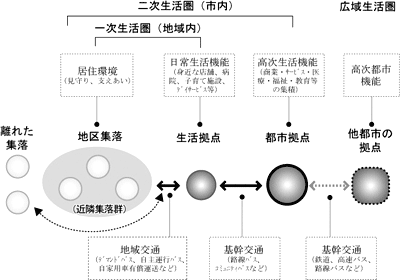
生活圏の階層化のイメージ
アルパックニュースレター169号・目次
「まちづくりとエリアマネジメント」
- 名古屋における協議会型まちづくりの紹介~広がり始めたエリアマネジメント
/名古屋事務所 尾関利勝 - 既成市街地における土地利用マネジメント~潮江密集地区のまちづくりの事例
/大阪事務所 岡本壮平・清水紀行 - 周辺市街地の土地利用マネジメント~非建築的土地利用の“状態”のコントロール
/大阪事務所 絹原一寛 - 地方都市の生活拠点のマネジメント~持続的な生活圏構造に向けて/大阪事務所 岡本壮平
- 住宅地の住環境マネジメント/大阪事務所 嶋崎雅嘉
- まちなかバルによるエリアマネジメントの第一歩/大阪事務所 中塚一
ひと・まち・地域
きんきょう
- 文化的転換/相談役(NPO平安京 代表理事)三輪泰司
- 「スマート・シュリンキングによる関西再生」まちづくり技術交流部会に参加しています
/京都事務所 石川聡史 大阪事務所 中塚一・絹原一寛・橋本晋輔 - 守山市でベンガラ塗りワークショップをしました/京都事務所 三浦健史







