アルパックニュースレター179号
『群れはなぜ同じ方向を目指すのか?群知能と意思決定の科学』
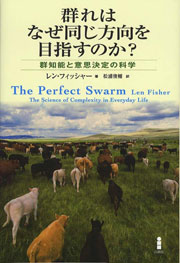
『群れはなぜ同じ方向を目指すのか?群知能と意思決定の科学』
本表紙
ミツバチはどうやって仲間を餌場に誘導するのか
ミツバチが餌のありかを巣の中の仲間に伝えるとき、ダンスを踊ることはよく知られています。踊り方によって餌場の方角と距離を表現するそうです。暗い巣の中でダンスを確認できるのはごく一部の仲間達、それでも目標を知っているわずかなミツバチが他の仲間の群れを餌場に導くことができます。こうしてミツバチは群れとして餌を見つけることができるのです。
このような集団としての知恵は、群知能と呼ばれています。本書は群知能の科学をわかりやすく解説したものです。
群れを形成するための三つの規則
動物行動学研究の成果によると、餌のありかを知っているミツバチが群れを餌場に導くためには、他の仲間に自分が目標を知っていることを明かす必要も、売り込む必要もないことがわかっています。つまり群れには明確なリーダーはいないということです。
一方、複雑性の科学からは、多くの社会的な動物や人間にも見られる群れを形成する集団行動の背景には次の三つの単純な規則があることが明らかにされています。
「回避(分離)」他の個体に衝突するのを避ける
「整列」近隣の個体群が向かっている方向を平均し、その方向へ向かう
「引き寄せ(結合)」近隣の個体群の位置を平均し、その方向へ向かう
複雑に見える動きも意外に単純な規則で動いているものです。
まちづくりと群知能
ところで、従来からまちづくりには優れたリーダーが必要だと言われてきました。上手くいっている取り組みには魅力的なリーダーがいることが多いものです。しかし、一方ではこれからのまちづくりは、リーダーよりもむしろファシリテーターの役割が重要であるとも言われています。カリスマ的なリーダーシップではなく、みんなをその気にさせ、つないでいくことでゆるやかに誘導していく、目立たないけれど重要な役割です。
このことは、仲間からリーダーと認識されなくても集団全体をある方向に導くミツバチの例と通じるものがあります。つまり、まちづくりには群知能が必要といえるのかもしれません。
発揮されなかった群知能
ワークショップの定番メニューに「月に迷ったゲーム」があります。月で宇宙船が難破し、遠く離れた母船まで戻るために必要なアイテムの優先順位を、個人とグループのそれぞれで考えるというものです。一般的な傾向として、個人で考えた結果よりもグループで話し合って決めた結果の方がNASAの模範解答に近くなり、群知能を実感できるというゲームです。
最近、あるワークショップでこのゲームをやったのですが、なんとメンバー全員がグループの答えより自分一人で考えた答えの方が模範解答に近かったというグループがありました。このグループでは群知能は発揮されなかったのです。
複雑性の視点からまちづくりを考える
再び動物行動学や複雑性の科学の成果に目を向けましょう。群知能が発揮されるためには「意識しようとしまいと他の個体たちが集団にとどまりたいと望んでいること、そして、相反する目的地を持っていないこと」が必要だそうです。まちづくりの言葉で言い換えれば「意識しようとしまいとみんなが自分のまちを愛していること、そして、ビジョンが共有されていること」とでもなるでしょうか。
先のワークショップの例では、メンバー間のコミュニケーションがぎこちなく、グループとしての気持ちの共有ができなかったことが群知能が発揮されなかった理由でしょう。こうしたこともまちづくりでは常識的なことですが、それは科学的にも裏付けられていることなのです。
アルパックニュースレター179号・目次
寄稿
ひと・まち・地域
- 地域から少子高齢化への対応を考える(その1)~女性就業率が高いと出生率も高い~/代表取締役社長 森脇宏
- 都市部の友好都市をねらえ!過疎地域の再生実験~京都府京丹後市(久美浜)×京都府木津川市
/地域産業イノベーショングループ 原田弘之・地域再生デザイングループ 森岡武 - 少子高齢社会対応ビジネス事例集を作成しました/地域産業イノベーショングループ 武藤健司・高野隆嗣
- 日本と台湾のビジネスマッチングを支援します/ 地域産業イノベーショングループ 高野隆嗣・江藤慎介・松田剛
- 中小企業が海外展開しても国内は空洞化しない!~関西中小企業の海外展開実態調査のご報告
/地域産業イノベーショングループ 江藤慎介・高野隆嗣
きんきょう
- 和歌の浦景観重点地区が指定されました/都市・地域プランニンググループ 絹原一寛・依藤光代
- みんなのNPOの活動報告!/公共マネジメントグループ 廣部出
- 小阪商店街の「若手」商店主が中心になって「まちゼミ」をしました
/都市・地域プランニンググループ依藤光代 - 新人紹介/地域産業イノベーショングループ 片野直子







