アルパックニュースレター197号
コミュニケーションツールとしてのまちづくり条例
-門真市まちづくり基本条例づくりに関わって-
地域再生デザイングループ/羽田拓也
まちづくり条例の系譜と門真市の取り組み
高度経済成長期には都市部への急激な人口集中に伴う宅地開発に対応するため、多くの自治体で開発指導に関する独自の手続きや基準を定めた開発指導要綱が作られました。しかし、法的根拠が薄弱で担保性が弱く、紛争が多発したことなどから、近年は徐々に要綱の条例化が進められてきています。こうした開発誘導や土地利用調整を目的とするものがまちづくり条例の一つのタイプです。
一方、市民主体による身近な地域のまちづくり、いわゆる地区まちづくりが広がるにつれ、条例によりこれらの取り組みを支える制度基盤づくりが進められてきました。まちづくり団体の認定と活動への支援、まちづくり計画等の提案の仕組みなどが主な内容です。こうしたまちづくり支援を目的とするものがまちづくり条例の二つ目のタイプです。
また、地方分権による権限の拡大とともに、地方自治体の自治能力の向上が求められるようになり、自治の基本理念や住民、議会、行政などの権利と責任、行政運営の仕組みなどを定める自治基本条例の制定が進んでいます。都市計画を含む行政施策の決定等にあたっての市民参加の手続きを規定する場合もあります。自治基本条例は広義のまちづくり条例といえます。
まちづくり条例には以上の3つの系譜があるといわれています。自治体によってはこれらの要素を全て盛り込んだ総合的なまちづくり条例を策定している例も見られます。
門真市では、高度経済成長期に形成された木造密集市街地の建物が更新期を迎えることから、従来の要綱に基づく指導からより実効性のある仕組みへの転換が求められるようになりました。一方で、平成26年には自治基本条例が制定されています。このため、都市計画や開発事業に関するルールを定めるまちづくり基本条例の検討が進められてきました。今回、私たちはこの条例づくりのサポートをさせていただきました。
門真市まちづくり基本条例の内容
門真市まちづくり基本条例は、全体で6章の構成になっています。第1章は、用語の定義のほか、市、市民、事業者の責務を定めています。
第2章は、まちづくりの基本とする計画として総合計画と都市計画マスタープランなどを位置付けています。地方自治法の改正で総合計画の位置付けが曖昧になっていることから、まちづくりとの関係を明確にすべきであること、市の都市計画の指針である都市計画マスタープランを市民や事業者も遵守すべきであることなどから、これらの計画が位置付けられることになりました。
第3章は、身近な地域のまちづくりの促進と活動への支援について定めています。
第4章は、都市計画の決定等の手続きとその際の市民参加の仕組みを定めています。また、これまで個別の条例として運用されてきた地区計画や建築協定に関する条例が統合されました。
第5章は、開発誘導の仕組みを定めた章で、本条例の中心的な内容となっています。従来の要綱の内容を継承しながら、大規模な開発行為に対する構想段階での届出の仕組みなどが新たに付加されることになりました。
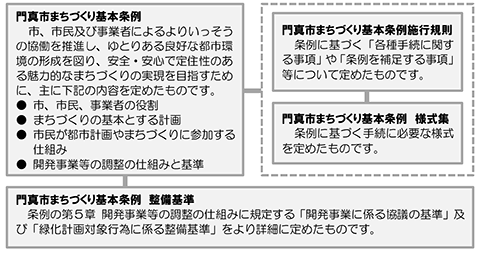
門真市まちづくり基本条例の体系図
条例検討におけるいくつかのポイント
条例の検討にあたって、いくつかポイントとなる論点がありました。以下では、主なものを簡単にご紹介します。
【開発誘導のフロー】
これまで「開発指導要綱」「中高層建築物等に関する指導要綱」「緑化に関する指導要綱」の3つの要綱によって個別に指導が行われてきましたが、条例化にあたってこれらの手続フローをまとめることが議論の俎上に上りました。しかし、指導の一貫性や事業者の混乱防止の観点から、それぞれが独立したフローとして継承されることとなりました。
【敷地面積の最低限度】
開発指導要綱では戸建住宅の敷地面積と共同住宅の占有面積の最低限度が定められていました。これらを条例に定めるのかどうか、また制限値が妥当かどうかが議論になりました。結果は、要綱にせよこれまで指導してきたという立法事実があること、制限値についても一定の根拠づけが可能であること、制限を設けることは都市計画法の趣旨とも不整合がないと考えられることから、戸建住宅の敷地面積については条例の本則に位置付けられました。共同住宅の占有面積はワンランク落として、条例に基づく整備基準とされました。
【罰則】
条例化の目的の一つである実効性を高めるため、罰則の導入が検討されました。議論の末、他都市の事例なども参考に、最終的には「勧告」「命令」「公表」の行政処分に止められ、罰則の導入は見送られました。これまでの要綱による指導との差が大きいこと、罰則を設けることによる問題点(要件に合致すれば必ず罰則を適用しないと不作為と判断される)などが主な理由です。加えて、罰則を設けて守らせるよりも、まちづくりの必要性を理解してもらうことや、協議の中で誘導していくことが重視された面もあります。
コミュニケーションツールとしての運用
条例づくりのサポートでは、最終的には条文そのものの案を作成することになります。当然ですが、条文には法律的な厳密性が求められることから、一字一句の持つ意味の十分な吟味が必要になります。「又は」「若しくは」、「及び」「並びに」の使い分けなどの法文テクニックだけでなく、句読点のつけ方一つにも気を使う作業です。
私たちは、考えたことを図、写真、言葉などのメディアを通して第三者に発信し、意図を伝えようとします。その際、うまく伝わるためには受取手の「共感」を呼ぶことが大切です。そして、そのためには発信者からの一方的な発信ではなく、伝えるべきものの性格や相手の立場を考えた伝え方を工夫することが必要になります。しかし、条文は「わかりやすく」伝えることよりも「正確に」伝えることが優先されるため、一読しただけでは非常にわかりにくい場合もあります。今回は、市民や事業者の方々の理解を助けるため、PRパンフレットと条文の逐条解説を作成しました。
ところで、まちづくりでは「共感」に基づく自発的な取り組みが重要ですが、例えば開発誘導などでは、時に厳密なルールや仕組みをつくって人々を「縛る」ことも必要になります。これは人々の行動のモチベーションに行政による「権力」を持ち込むことです。ただし、それがうまく機能するためには行政と市民や事業者との信頼関係が不可欠です。そのため、条例の運用にあたっては、規定に基づいて淡々と手続きを進めるのではなく、条例の趣旨を「共感」してもらうためにも「協議」や「調整」というコミュニケーションを重視するスタンスが求められると思います。まちづくり基本条例は、まさにそのためのコミュニケーションツールであるともいえるのではないでしょうか。
アルパックニュースレター197号・目次
アルパックチーム紹介
ひと・まち・地域
- 「東北を旅して、日本を考える」~うまいもんがいっぱい、三陸へ行こう。~/高田剛司・片野直子
- コミュニティデザインによる南港ポートタウンの魅力発信!/嶋崎雅嘉・戸田幸典・橋本晋輔
- 京都のまちを元気にする、空き家の再生・活用に取り組んでいます!/杉原五郎・松本明・嶋崎雅嘉・戸田幸典・竹井隆人
- コミュニケーションツールとしてのまちづくり条例-門真市まちづくり基本条例づくりに関わって-/坂井信行・水谷省三・中井翔太・羽田拓也
- (仮称)此花区エクソダス大作戦~此花区民は大阪城をめざす!~/清水紀行・石川聡史・松下藍子・中井翔太・坂井信行
- 地域から少子高齢化への対応を考える その16~人口増加の参考になる可能性がある基礎的自治体/森脇宏
- ネパール・ゴルカ地震から1年/堀口浩司
きんきょう
- 伝承譜 その2 継承者の心構え/三輪泰司
- 高槻市の摂津峡が盛り上がっている!その2/片野直子・高田剛司
- 南河内郡太子町~健康づくりの取り組み紹介/中井翔太
- 「ママ起業」と子育て中の母親の生活満足について~職場復帰のご挨拶~/依藤光代







