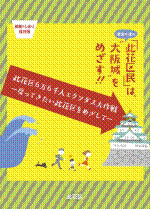アルパックニュースレター197号
(仮称)此花区エクソダス大作戦~此花区民は大阪城をめざす!~
此花区民は大阪城をめざす
大阪市此花区は、ほぼ全域が海抜1.0m以下の地盤高となっているため、南海トラフ巨大地震により発生する津波対策に積極的に取り組んでいます。
ご承知のとおり、津波から命を守るためには高台に逃げることが重要です。しかし、此花区のように沿岸部にある地域では、すぐ背後に小高い丘等があるわけではありません。そのため、津波避難ビルへの迅速な避難(垂直避難)を推奨し、まずは区民6万6千人が全員生き残ることを目指しています。
津波が引いた後も一旦水に浸かった建物ですぐに暮らすことはできません。そのため、しばらくは大阪市内の「高台」である上町台地の大阪城公園で避難生活することが考えられました。此花区民みんなで“大阪城”をめざす、名付けて「此花区エクソダス大作戦」です。
今回、私たちは6万6千人の区民を大阪城公園まで安全に避難させるための避難計画、いわば「大脱出計画」づくりをお手伝いしました。
戻ってきたい此花区をめざして
今回、私たちが重視したのは、「此花区に再び戻ってくる」という意思表示です。津波被害によって当面の間は元の生活に戻ることは困難だと考えらえます。しかし、だからといって生まれ育った此花区を捨てるために脱出するのではなく、再び此花区に戻ってこよう、という思いを皆さんで共有することが災害への備えにおいても重要だと考えたからです。
そのため、計画のリーフレットでも「大阪城へ逃げよう」ではなく「戻ってきたい此花区をめざして」というフレーズを採用しました。
大人数・大集団による長距離の移動
今回の計画策定にあたっては、「大人数・大集団による長距離の移動をいかに安全かつ効率的に実施するか」が重要なポイントでした。 そのため「どのルートで移動するか」「集団を統率する体制づくりをどうするか」「顔見知り、見知らぬ人が混在する集団でいかにコミュニケーションを図るか」等について、文献調査のほか学識者や自衛隊OB等へのヒアリングや等をもとに検討を進めました。 そのなかで見えてきたのは、「集団行動の必要性に対する認識」「メンバー間の信頼関係の構築」「リーダーシップの発揮」「集団の秩序の維持」の4点です。そして、その4つを支える上でも「平時のコミュニケーション」が重要であるということを感じさせられました。
検証訓練:大阪城までの10kmの道のり
計画案の作成後、区民の皆さんに協力いただき検証訓練を実施しました。午前は「グループづくり」、午後は「大阪城への移動」「ふりかえり」という2つのプログラムを実施しました。
「グループづくり」では、区民の方々に仮想の役割(Aさんは高齢者役、Bさんは子ども連れのお母さん役など)を与え、それぞれの立場でグループ形成、歩行時の並び方などを考えてもらいました。
午後は、午前に作ったグループ単位で実際に大阪城まで歩きました。約10kmの行程をリーダー役の人はグループ全体の様子の確認、メンバーの方はルートの状況やお互いの体調等を気遣いつつ、約3時間かけて大阪城まで踏査しました。
ふりかえりワークショップでは、「声をかけあいながら歩くのが安心感につながった」「今回は区役所が青パトなどを並走してくれたのが良かった」「後半疲れてくるのでこまめな休憩が必要」といった意見がありました。一方、「災害時にこれだけの距離を歩くのは現実的ではない」「心理的な問題はあるが地盤の高い舞洲も避難地の選択肢になるのでは」といった意見も出ました。
 検証訓練の様子 |
 検証訓練で使ったフラッグ |
コミュニケーションから始まる防災
ヒアリングやふりかえりワークショップでもいろいろと素朴な疑問が出されました。「そもそも此花区民が行く前に近くの住民で公園はいっぱいになっているのではないか」とか「高層階に住んでいる人は避難する必要はないのではないか」などなど。まさにご指摘のとおりです。突っ込みどころが満載の計画です。もちろんそれらは想定内の話であり、他区との調整も含め、今後も引き続き検討していくべきものです。
今後、区民の皆さんが日頃から取り組まれている防災訓練の中にも今回の計画のエッセンスを取り入れたプログラムを組み入れていくことも重要です。特に、平時から他者とのコミュニケーションをいかに図っていくか…これは行政主導でできるものではありません。「自分の考えを押し付けない」「異なる意見も受け入れる」「相手の立場を理解する」など当り前かもしれませんが、そんな些細なことを普段の生活の中で一人ひとりが意識する必要があると思います。
来るべき災害に備えて私たちができること
おりしも4月17日未明に熊本大地震が発生しました。今回、津波災害はありませんが、長期間に渡る余震で、現在も多くの方が避難生活を余儀なくされています。改めて私たちの生活から災害は切っても切り離せないということを再確認させられました。南海トラフ巨大地震は確実にやってくるのです。今回の計画づくりや避難訓練は、いつかやってくる災害に備えるためのほんの一歩にすぎませんが、これをやったからこそ気づいたことが区民の方にとっても私たちにとってもあったのではないかと思います。
災害による被害はまちの中に平等にもたらされるのではなく、弱いところに集中します。災害という大きな出来事をきっかけに、そのまちが抱えている様々な課題が表出するのです。災害の被害を少なくし、被災後に創造的な復興を遂げていくためには、日頃からまちが抱える課題ときちんと向き合っていくことが必要ではないでしょうか。「平時のコミュニケーション」が重要であるように、今直面している課題を些細なことでも一つひとつを解決していくことが防災につながっていくのではないかと思います。私たちも微力ながら、そんなまちづくりのお手伝いができればと考えています。

ワークショップ
アルパックニュースレター197号・目次
アルパックチーム紹介
ひと・まち・地域
- 「東北を旅して、日本を考える」~うまいもんがいっぱい、三陸へ行こう。~/高田剛司・片野直子
- コミュニティデザインによる南港ポートタウンの魅力発信!/嶋崎雅嘉・戸田幸典・橋本晋輔
- 京都のまちを元気にする、空き家の再生・活用に取り組んでいます!/杉原五郎・松本明・嶋崎雅嘉・戸田幸典・竹井隆人
- コミュニケーションツールとしてのまちづくり条例-門真市まちづくり基本条例づくりに関わって-/坂井信行・水谷省三・中井翔太・羽田拓也
- (仮称)此花区エクソダス大作戦~此花区民は大阪城をめざす!~/清水紀行・石川聡史・松下藍子・中井翔太・坂井信行
- 地域から少子高齢化への対応を考える その16~人口増加の参考になる可能性がある基礎的自治体/森脇宏
- ネパール・ゴルカ地震から1年/堀口浩司
きんきょう
- 伝承譜 その2 継承者の心構え/三輪泰司
- 高槻市の摂津峡が盛り上がっている!その2/片野直子・高田剛司
- 南河内郡太子町~健康づくりの取り組み紹介/中井翔太
- 「ママ起業」と子育て中の母親の生活満足について~職場復帰のご挨拶~/依藤光代