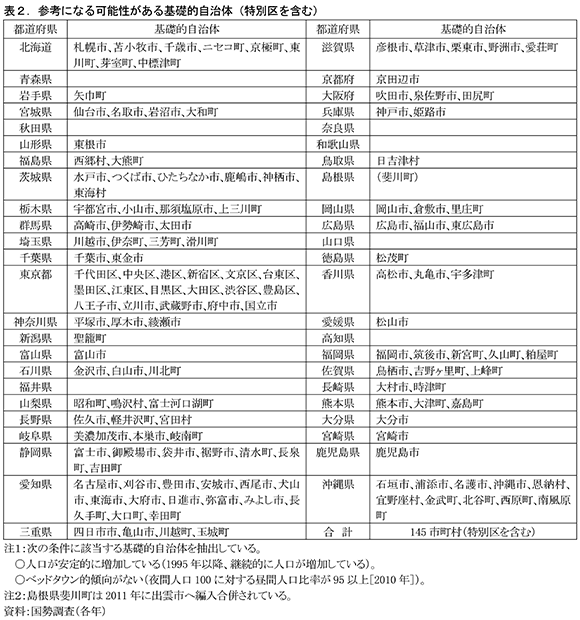アルパックニュースレター197号
地域から少子高齢化への対応を考える その16
~人口増加の参考になる可能性がある基礎的自治体~
前号まで4回にわたって、北海道で人口が増えている3つの町を抽出し、それぞれの人口増加の要因について考察してきました。増加要因は自治体によって様々でしたが、「地方消滅」(増田寛也編著)において「未来日本の縮図」と記されていた北海道でも、それぞれの特徴を活かした地域づくりによって人口が増えている自治体があることが確認できました。
今号からは、これまで北海道で考察してきた観点を踏襲しながら、対象を全国の自治体に広げ、人口増加自治体の増加要因を考察していこうと思います。
人口が増えている基礎的自治体数
2005年から2010年にかけて人口が増えている基礎的自治体数(特別区を含む)は、表1に示すように全国で430あり、全国の基礎的自治体総数1741の25%を占めています。この数字は、3/4の自治体の人口が減っているという厳しい実態を示していますが、同時に一律に厳しい訳ではなく1/4の自治体の人口は増えており、その要因を学び取ることの重要性も示していると読み取れます。
また、人口増加自治体は、首都圏や愛知県等に多いのは事実ですが、北海道を含む地方部でも人口増加自治体は存在していますので、地方部でも人口増を実現できる可能性を示しています。
参考になる可能性がある基礎的自治体
それでは、人口が増えている430の自治体はすべて、他の自治体の参考になり得るのでしょうか。そう簡単ではなく、たまたま特別な事情で2005年から2010年に人口が増えただけで人口減少の構造が続いている自治体や、大都市のベッドタウンとして人口が増えているだけの自治体は、参考になりにくいので除外することにします。具体的には、1995年から人口増加が継続していて、昼夜間人口比率(夜間人口100に対する昼間人口の比率)が95以上(2010年)の自治体であれば、参考になる可能性があると考えることにしました。このように考えて整理すると、表2に示すように145の自治体が「参考になる可能性がある基礎的自治体」として抽出できました。
これらの自治体の人口増加要因は様々だと思います。北海道の3町に関する考察でみたように人口増加の対策に特効薬はなく、地域づくりの様々な施策や活動等が相乗効果を発揮して、人口増加をもたらしていると理解すべきだと思いますが、その様々な取り組みの根幹には、自治体ごとの「基本的な考え方」があるように思われます。ちなみに、こうした「基本的な考え方」と、昨年度に各自治体が策定した地方創生の総合戦略は、通底するものですので、1年でどこまで肉薄して策定できたのか、今後を見守りたいと思います。
次号以降、これら145の「参考になる可能性がある基礎的自治体」の中から、大都市圏というアドバンテージを持たない地方部の自治体を中心に、特徴的な傾向を有する自治体を抽出し、それぞれの増加要因を探ることを通じて、多様な取り組みの根底にある「基本的考え方」を幾つか積み上げてみようと思います。
アルパックニュースレター197号・目次
アルパックチーム紹介
ひと・まち・地域
- 「東北を旅して、日本を考える」~うまいもんがいっぱい、三陸へ行こう。~/高田剛司・片野直子
- コミュニティデザインによる南港ポートタウンの魅力発信!/嶋崎雅嘉・戸田幸典・橋本晋輔
- 京都のまちを元気にする、空き家の再生・活用に取り組んでいます!/杉原五郎・松本明・嶋崎雅嘉・戸田幸典・竹井隆人
- コミュニケーションツールとしてのまちづくり条例-門真市まちづくり基本条例づくりに関わって-/坂井信行・水谷省三・中井翔太・羽田拓也
- (仮称)此花区エクソダス大作戦~此花区民は大阪城をめざす!~/清水紀行・石川聡史・松下藍子・中井翔太・坂井信行
- 地域から少子高齢化への対応を考える その16~人口増加の参考になる可能性がある基礎的自治体/森脇宏
- ネパール・ゴルカ地震から1年/堀口浩司
きんきょう
- 伝承譜 その2 継承者の心構え/三輪泰司
- 高槻市の摂津峡が盛り上がっている!その2/片野直子・高田剛司
- 南河内郡太子町~健康づくりの取り組み紹介/中井翔太
- 「ママ起業」と子育て中の母親の生活満足について~職場復帰のご挨拶~/依藤光代