アルパックニュースレター177号
『大阪アースダイバー』
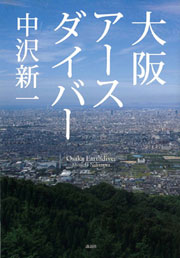
『大阪アースダイバー』本表紙
都市を読み解くアプローチ
私たちが通常、都市を読み解くときには次の三つの視点からアプローチしています。
一つ目は地形です。地形は都市の成り立ちに関わるもっともプリミティブな要素といえます。地形によって秩序づけられ、関係づけられたところに領域が生まれ、それが私たちが認識する都市空間へとつながっています。
二つ目は歴史です。いうまでもなく、現在の都市は先人が営々と築き上げてきた歴史の蓄積の上にあるものです。どのような経過をたどって現在の姿に至ったのか、歴史を振り返ることは都市を読み解くうえでは不可欠な要素です。
そして三つ目は人びとの営みです。都市の中には人びとのさまざまな営みがあります。それは暮らしであったり経済活動であったりします。都市の「生きた」姿を捉えるためには、人びとのアクティビティに着目する必要があります。
アースダイバーの方法
中沢新一氏が提唱するアースダイバーの方法は、こうした私たちのアプローチとは少し視点が異なっています。東京を舞台とした前著『アースダイバー』では次のように述べられています。
「人間の心のおおもとは泥のような「無意識」であり、私たちは無意識をこね上げて社会をつくってきた。泥を材料にしてつくられてきた人間の心という陸地が水中に沈みかけている、そこで水の中に潜って底のほうから一握りの泥をつかんできて、それを材料にしてもう一度人間の心を泥からこね直す、そんな気持ちで東京を見回してみると、これまで気づかなかったものが見えてきた。」
縄文時代に遡って地質の分布を追っていくと、固い岩盤をもった洪積層と河川が運んできた土砂の積もった砂地の多い沖積層に大別できるそうです。そして洪積層には乾いた文化が息づき、沖積層には湿った文化が息づく、こうした考え方にそって都市の成り立ちを読み解いていくのがアースダイバーの方法です。
大阪をアースダイブする
ここまでは東京を対象にした話。今回取り上げる『大阪アースダイバー』ではかなり様子が違っています。
大阪は洪積層と沖積層といったシンプルな二分法では説明できないのです。大阪の中心部の土地は水中から「生成」したのであり、大阪は東京のように洪積層の台地にできた都市ではなく、やわらかい無定形の土砂の上にできた都市である、そのため空間の感覚を秩序づける何らかの座標軸が必要になってくる、というのです。そして、その座標軸として示されているのが上町台地に沿った南北軸と、生駒山へと向かう東西軸であり、南北軸は権力を表す「アポロン軸」、東西軸は生と死の循環を表す「ディオニュソス軸」と名づけられています。
そしてもう一つ、海民出身の商人が二つの軸の脇あたりで不定形な島々の上につくった「ナニワ」、この三つのトポロジーの組み合わせで大阪はできていると。トポロジーというのは柔らかい幾何学のこと。絶えず変化をとげてきた大阪には表面上の形は大きく変わっても、一貫して変化しにくい深層の構造があるとも。学術的根拠はともかく、こうした構想力は非常に独創的だと思います。
都市を再編集する方法としてのアースダイビング
アースダイバーは厳密な史実に基づいているわけではないため創作にすぎない、といった批判も一部にはあるようです。しかし、人びとを惹きつける非常に魅力的な方法であることは間違いありません。歴史を読み解くというよりもむしろ、新しい視点から都市を再編集していく、まちづくりの今日的アプローチの有力な方法の一つとして捉えていくこともできるのではないでしょうか。まちづくりにかかわる者にとって、前著の『アースダイバー』とともに本書は貴重な示唆を与えてくれるはずです。
アルパックニュースレター177号(新年号)・目次
新年の挨拶
ひと・まち・地域
- 三重県の新しいお米「結びの神」が誕生!
/産業・地域経済イノベーショングループ 原田弘之・武藤健司 - エネルギーの「見える化」!豊中市での市民向け省エネ推進社会実験
/環境マネジメントグループ
山﨑衛・中川貴美子・森野真子・畑中直樹 公共マネジメントグループ 石井努 - びわ湖の森を元気するkikitoの取り組み~ニュースレター今号は“森林整備に貢献する紙”で発行
/環境マネジメントグループ 中川貴美子・畑中直樹 - 期間限定サブリースPROJECTによる大和・町家の利活用
/地域再生デザイングループ 岡崎まり・嶋崎雅嘉・中塚一
きんきょう
- 地域に根ざして30年/名古屋事務所 尾関利勝
- 堺高校発、学校から始まるエコな建物の使いこなし/環境マネジメントグループ 畑中直樹・森野真子 建築プランニング・デザイングループ 原田稔
- 震災復興と観光のチカラ/公共マネジメントグループ 高田剛司
- 都市を計画する仕事のこれから/代表取締役会長 杉原五郎
- アイスポットニュース/都市・地域プランニンググループ 絹原一寛







